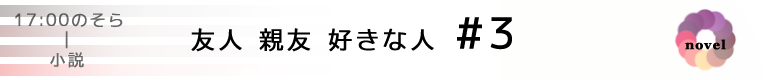日の入りしているが辺りはまだ明るい。しかし室内では暗過ぎるのだろう、明かりのついた住宅が殆どだ。
公園の出入り口に立ち、辺りを見渡す。
植木に囲まれたこの小さな公園には、数台の遊具とベンチがあるが、今の時間には利用している者はいない。
いや、一人の高校生が遊具で遊んでいる。
とても険しい表情で、ブランコで遊んでいるだいちゃんを発見し、先ほど感じていた疲労感など早速吹っ飛んでしまった。
――なに、あの何者にも邪魔はさせまいと言う表情は。
そんな感慨とは裏腹に、とりあえず来てくれたという安堵感が私を支配する。
そしてちぃとの約束を思い出す。
――必ず私から告白すること……か。
これまで一度もされた事の無い告白。いや、屋上での一件を考えるとそうではないのだが、あれはノーカンだ。大切な言葉を聞いていないし、言われる前に押し留めたのだから。
だからこそ私からの方が良いとちぃは言う。
そんな経験は今までにした事はない。
これまでの学校生活は男子を避けたものだったが、やはり好きになってしまう子は居た。しかしそれも片想いで終わっているし、自分から告白してみようなんて考えたことは無かったのだ。
不安が増す。
私は一度、屋上でだいちゃんを拒んでいるし、明確な言葉を聞いた訳ではない。
ちぃの話では私を好いている事になってはいるが、この短期間でだいちゃんの気が変わっていないとは言い切れないのだ。
そう。二度目の屋上で、私は最悪の事をしでかしている。
ちぃは言っていた、だいちゃんには何一つ相談していないと。
今回の事は、ゆーことちぃが共闘して創り上げようとしたシナリオだが、それにだいちゃんは一切関与していない。
そうするとどうだ。だいちゃんは本気で私に嫌われていると思っているのだろうし、既に私の事を嫌いになっているかも知れない。あんなに酷い事をしたのだ、当然と言える。
先ほどから悪い方にしか頭は働かず、不安がさらに増し、脅えてしまう私が居る。
こんな事では駄目だ。あれだけちぃに激励されたのだ。私が怖気づいたりなんかしてられない。それに屋上での私を見ても尚、ここに来てくれている。
今はその事実にしがみつく他ない。
一歩を踏み出す。
踏み固められた小さな砂利が、私の決意と共に音を生し、その音をキャッチしたのだろう。だいちゃんが私に気づき、ブランコから降りた。
そしてお互いに近づき、当たり障りの無い会話からスタートした。
調子はどうかと訊ねれば、ぼちぼちだと返ってくる。
右頬はどうしたと聞かれれば、大丈夫と返す。
そして、私は頭を下げ、謝罪した。
「屋上ではごめんなさい。あんな言い方ないよね。反省しています」
心臓の音がとても大きく、辺りにひしめいているだろう様々な音が聞こえなくなる。
そして未だ、だいちゃんの顔を直視できていないが、どのような表情をしているのだろうと気になってしまう。
怒っているだろうか。それとも私を鬱陶しく思っているのだうか。事情はどうあれ、酷い事をしてしまったのだ、どう思われようと仕方がない。
そう考えると益々顔を上げることが難しくなるのだが、私自身、今は謝ることしか出来ないのも事実だ。だいちゃんに許しを貰えるまで、どうにか謝り続けるしか無い。
恐怖はあったが、意を決して顔を上げる。
――とても驚いてるね。
声に鳴らない様子で、だいちゃんはその場に立ち尽くしていた。
結構な時間をなにも反応せずに居るので、私は躊躇いがちに声を掛ける。
「あ、あのう……。だいちゃん?」
「あ? ああぁ、すまん。行き成り謝られたからさ。ちょっと驚いた」
「気にしてなかったの?」
「いや、あの晩はちょっと立ち直れない位に落ち込んでたし、お前から連絡くるまで、かなり参ってたかな」
それは当然だ。あんな拒絶を目の前にしたら誰だって落ち込む。
私の表情の所為だろう。だいちゃんは慌てた様に付け足す。
「でもさ、あれは俺も悪かったかなって思ってたんだ。ちぃの様子もおかしかったし、何かあったんだなって勘づいていたんだけどな。ごめん。タイミング悪かったよな」
今度はこちらが呆ける番だった。
だいちゃんに謝られる事など何も無い。それでもだいちゃんは頭を下げたのだ。
その事に少なからず嬉しいと感じていた。だいちゃん自身、自分の事で精一杯だったろうに、私たちの事を気に掛けてくれていたのだ。
表情が自然と綻んでゆく。私の表情が移ったかのように、だいちゃんの表情も和らいでゆく。
「解決……、したみたいだな」
「うん」
そうかそうか。そう呟き胸を撫で下ろすだいちゃん。
「許して……、くれるの?」
「許すも何も、お前にも色々あったんだろ? 俺も無神経なところがあったように思うし、あれはやっぱりタイミングが悪かったと思ってるよ。それにあんなお前も見れたからさ、特をしたって言うか、うん、お前の一面を見れて良かったよ」
どこかちぃに似ている気がした。
他人を思い遣れる気持ちをだいちゃんも持っている。
屋上で見せた私の態度に、少なからず傷ついている筈なのに、私を理解しようとしてくれている。
優しさとは違う。その何かを私は持っているのだろうか。
気合を入れ直すだいちゃんは、あの時の真剣な眼差しで私を見つめる。
「じゃあ俺の話、聞いてくれるか?」
屋上での事が思い起こされる。
この真剣な眼差しは、私に想いを伝えようとしているのだろう。それだけで安堵し嬉しくなるのだが、急に恥ずかしくなり、だいちゃんを直視できなくなる。
しかしそうも言ってられない。
ちぃとの約束。
これだけは果さないといけない気がする。
「ちょ、ちょっと待って。私の話からじゃあ駄目?」
「……話って?」
話の腰を折られ、少し不満げなだいちゃんを待たせ深呼吸をする。
ここまで来てなんだが、やはり怖気づいてしまう。
告白なんてしたことがないし、どこか遠い夢物語なのだと内心思っていたのだ。
ここまで明確に相手の気持ちを知ってても尚、緊張してしまい、恐怖するものなのだろうか。
不振がるだいちゃんを余所に、気持ちを落ち着けようとするが、なかなか上手くいかない。あまり待たせるのも悪いと思い、不安定な気持ちのまま言葉を口にする。
「あ、あのね。その……」
言い淀んでしまうが勢いを付けてしまえばいけそうだった。
「あの! 私、私ね! だいちゃんの事が!」
「ちょっと待った!!」
……止められました。
え? 止められた!?
「落ち着け。というか、こういうのは男からって決まってるだろ?」
「え。そんな法律ないと思うけど……」
「いやいや、違うって。常識でさ。こう、男からの方がかっこいいだろ」
変な拘りを持っているようだった。
「でもちぃと約束したの。私から言わなきゃ駄目って」
「はぁ。……あいつ」
そう落胆した直後だ。だいちゃんの中で屋上の件がフィードバックしたのだろう。これまで見たことの無い様子で慌てる。
「違う! 今のは違う! ちぃがどうのこうのじゃないんだ。いや、なんつうか、その、これだけは譲れなくて、あいつもその事知ってるからさ。俺を困らすために……」
私は頬膨らませ、だいちゃんを睨む。
しかしこれは憤慨の表れではない。そんな睨みでもだいちゃんには大ダメージなのだろう。冷や汗をそのままに固まってしまう。
「あ、あの俺、また失敗したか」
「うん。失敗した」
恥ずかしくて視線を逸らすが、頬が異常なまでに熱くなってゆく。
「やっぱり、二人は仲がいいなぁって、思って……」
今までこんなに恥ずかしくなってしまう出来事はあっただろうか。
いや、無い筈。
「……嫉妬、か?」
告白する前に死んでしまいそうだ。
「そうか。はぁ、良かった」
「よ良くないよ! 私は!」
ぽん。
そう私の頭に手を乗せるだいちゃんは、とても穏やかな表情をしていた。
「ありがとう。ってのも、おかしいかな。でも、嬉しいよ」
……うぐ。
なにも言い返せない。
「どうしても譲ってくれないのか?」
こくりと頷く。
ちぃとの約束だ。それに私から言わなければならない様な気もする。
ゆーこに、ちぃに、そしてだいちゃんに一杯迷惑を掛けたのだ。これはけじめの様な物なのかも知れない。
「だいちゃんこそ、譲ってくれないの?」
自然と上目遣いになってしまう。
「そ、そんな目をしても駄目だ。譲っても良いかなとも一瞬思ったが、これだけは譲れん」
「そう……」
これは使うしかないのか。
許してもらえない時の解決法は、ちぃから教わっていた。状況は違うが、使ってみるのも手かもしれない。
私は徐にスカートの裾へ手を掛ける。
死ぬほど恥ずかしいが、ちぃとの約束を果たさない訳にはいかない。
「ここれで。だから譲って下さい!」
そうスカートをたくし上げようとした時だ。
私の手を掴み。怒鳴るだいちゃん。
「ちょっと待て! これもちぃの入れ知恵か!?」
「……う、うん。見せれば一発だって……」
「信じたのか? って信じたんだよな……」
微妙な空気が流れ始める。
傍から見たら、スカートを捲られるのを必死で抑えている様に見えただろう。イコール。だいちゃんが痴漢男役ということだ。
ここで私が助けを呼び叫べば、めでたく痴漢男になるのだろう。
「……少し、落ち着こう」
同意するしか無い。
手近なベンチに並んで座り、だいちゃんが買って来てくれたホットウーロンを一口飲む。
辺りは静かに時間を刻み、街灯がなければ暗い夜道になる寸前の時間帯。
未だ緊張は解れないが、私を落ち着かせるものがある。
ちぃとゆーこがくれた安堵感もそうだろうが、今はだいちゃんの存在が殆どなのだろう。
こんなにも落ち着いてしまう自分が、少し恥ずかしい。
ふと、聞きたいことが自然と口から滑り降ちる。
「どうして、ちぃを好きにならなかったの?」
「どうしてだろうな。なんつうか、ちぃはもう兄妹のようなものなんじゃないかな」
驚き、困ったような、だけど微笑を湛えている。
「生まれた時から傍にいるし、喜びも、楽しみも、怒られた時だって一緒だったんだ。……俺もお前と同じこと考えた時はあるよ。ちぃの幼馴染だってだけで胸を張れそうなくらいに、あいつはいい奴だ。だからこそなのかな、ちぃとは友達以上とか、恋人未満とかじゃない。別の枠組にいる気がするんだ」
真っ直ぐに前を見遣り語るだいちゃんは、どこか楽しげに話している。
それこそ、ちぃがだいちゃんの事を話す様に、大切な気持ちを共有したくて仕方が無いというような口調だ。
「……ちぃから聞いたんだけど。背の高い人が好みなの?」
「はは、あいつそんな事気にしてんの? それは偶然。ってか、ちぃが低すぎだからそう思ってるだけじゃないのかな。俺の場合、背の高さとはあまり気にしたことはないよ」
「……」
「さっきも言ったけど、ちぃは別の、それこそ家族同然の付き合いをしてきたからな。俺は俺の気持ちに素直になってるだけだよ。だけど、なんだろうな。大人になって、それこそ三十路近い歳にさ、落ち着ける相手を探しだしたら、ちぃの方を向くかも知れないな」
まぁ、その頃には手遅れかもしれないけど。そう付け足し、ふとこちらを見遣るだいちゃんと視線が合う。
興味なかったか? 小首を傾げ微笑むだいちゃんは、とてもやさしい表情をしている。なんだか気恥ずかしくなってしまい、曖昧に相槌を打ってしまう。
私たちの歳で、それこそ結婚なんてものは未だ遠く、想像すらしない所にあるのだろうけど、やはり、少し妬いてしまう。その歳まで私たちが傍にいるとも限らない。しかし、この関係がずうっと続いてて欲しいと願う気持ちも、またここに存在している。
不意に頭に暖かく固いものが乗る。
……コーヒー缶でした。
「ごめんごめん。ちょっとアンニュイ表情になってたからさ。……その、大丈夫だよ。俺はその歳の先まで、ずっとお前と一緒に居られるといいなって思ってるし、居られるよう努力を惜しまないつもりだよ」
くすくすと笑うだいちゃんに私は頬膨らませ対向する。
うむ、俺はそんな顔も好きだからなんとかなりそうだ。そう言って無邪気に微笑み、缶コーヒーを手に取る。
と、その時だ。
二人して見つめ合い、確認するかのようにお互いを凝視する。
「……いま」
「違う! 今のは告白とかじゃない! そのあれだ、好みの話だ! カレーが好きとかその程度の」
「その程度ってのも、ちょっといやかも」
「う……、だよなぁ」
数秒の沈黙の後、どちらともなく笑いあう。
変なところに拘ってしまう私は、だいちゃんと同じなのかも知れない。
「なんだかな。いい感じのを考えてたんだけど、無駄になった」
「ちょっと気になるかも」
「お。聞きたいか?」
「今は嫌」
こそばゆい会話と静かな雰囲気。
そして自然と視線が合い数秒ののち。
「好きだよ」「好きです」
私たちは想いを伝え合った。
公園を出る時に、ふと手を差し伸べてくれた。
暖かく大きな手が、優しく私の手を握ってくれている。
辺りは暗く、住宅から漏れ聞こえる生活音が静かに私たちを包み込む。
街灯の下をゆっくりと歩く歩幅は、私に合わせてくれているのだろう、そんな優しさが今は嬉しく、気恥ずかしかった。
隣を歩くだいちゃんを見上げる。
他愛のない会話。
大きな左手。
大好きな笑顔。
それを確認し、親友とはまた違った存在なのだと認識する。
それがなんなのか、まだ明確には示すことは出来ない。
似たような感情はある。
しかしそれとはまた違った感情も存在する。
これから少しずつ理解していくのだろうが、理解しなくても良いような気もしてくる。
決して疎かにしている訳ではない。
この感情は二人で見つけていきたいという衝動。それに理解しなくても、私はずうっと傍にいたいと想えている。
大丈夫。答えは必ず見つかる。
ふと気づいた時に此処に在るような、そんな気がするのだから。
◆ ◆ ◆
カーテンの隙間からは真新しい朝日が射しこみ、薄暗い室内に一筋の光が小さな明かりを作っている。
いつもより早くに目が覚めてしまい、もう一眠り出来るような時間帯ではあったのだが、眠気は全く無かった。かと言って、布団から出るのも惜しいような気がして、横になったままカーテンから差し込む光を飽きもせずに見ていた。
つい昨日の私とは打って変わった様子に驚きはするものの、昨日の出来事を思い出すたびに、忘れてはいけない出来事なのだと再認識する。
私はどうしようもなく弱い人間なのだ。
一時の感情に流され、辛い事からも背を向けた。
自身を知らず、確固たる決意もあの時は持ち得ていなかった。
だからこそ強くなりたいと思える。
私自身、昨日とは違い日々成長しているのだろうが、あの暗闇に屈してしまわぬように、強くなりたいと決意したのだ。だからこそ忘れる訳にはいかない。
あの痛み、あの苦痛、あの悲しみが私を強くするのであるならば、一生背負う覚悟を持たなければならない。
そんな感慨を苦笑と共に、心の片隅に追いやろうとした時、けたたましい音と共に目覚まし時計が覚醒する。
何時ものように、緩慢な動作で目覚まし時計をなだめ、出かける支度をした。
私の様子を見て両親から一言二言あったが、それは昨日の様な心配からの物ではなく、少しくすぐったくなるような物だった。私自身全く自覚はないのだが、どこかニヤケていたらしい。
そしていつもの時間から少しだけ早い通学路。
空気は澄み切っており、一口吸うたびに私の背中を押してくる。
ここまで劇的な変化に、昨日の出来事は夢うつつの幻なのではと疑ってしまうが、私の中を支配するものがそうではないと訴えてくる。
平常心、平常心。そう言い聞かせる気持ちとは裏腹に、やはり誰もいない待ち合わせ場所に、何時もよりも早くに到着する。
足早に駅構内へと姿を消すサラリーマン、私と同じ制服を着た学生、様々な人達が私の前を通り過ぎてゆく。
そんな有り触れた光景に対し気の向く方へと視線を泳がせている時だ。
「おっはよ!」
挨拶と共に私の目の前に立つちぃは、満面の笑みで顔を飾っている。
そんなちぃに圧倒されてしまうが、それはほんの数秒のこと。
私の顔には自然と笑みがもれる。
「おはよう」
そしてそのちぃの後ろには、だいちゃんが少し気後れした様子でいる。
視線が合い、どちらともなく微笑み合う。
おはよう。何時ものように交わす挨拶もどこか気恥ずかしくなってしまうのだから、今の関係は少し難しい。
ニヤニヤと私を見遣るちぃをどの様に突っ込み、あしらえば良いのか分からないのだから、これまた少し戸惑ってしまう。
「ったく、朝からイチャ付かないでもらえると助かるんだけど?」
ゆーこだ。
不満そうな声色とは違い、微笑のゆーこが合流する。
それぞれに挨拶を交わし、誰ともなく歩き出す。
何時ものようで、何時もとは違う歩幅が、それぞれにそれぞれの音を奏でていた。
前を歩くちぃとゆーこは、どこか楽しそうな雰囲気だ。
隣を歩くだいちゃんへと視線を向ける。
やはり、どこか恥ずかしそうにそっぽ向いているが、ふと視線が合うと、何かに観念したかのように話しだす。
「なんつうか、やっぱ恥ずかしいな」
私もそうだ。何を話していいのか分からないし、少しテンパッている。
「よく考えるとさ、昨日のあれも、かなり恥ずい事言ってたよな。今朝、目が覚めた時に自覚したよ」
そうなのだ。私の場合、色々なことがありすぎて、その場の雰囲気に酔っていたのかも知れない。
だからこそかな、全ては夢で幻なのではという思いもあった。
確固たる証が無かったからだ。
だからこそ、今朝の私はどこか落ち着きがなく、何時もの時間よりも早くに待ち合わせ場所に到着してしまったのだ。
しかしみんなの顔を見て、それが夢ではないことを実感している。
「だからさ、なんか恥ずかしいし、本当は先に学校へ行くつもりだったんだ」
「え? そうなの?」
「いや、まぁそんな顔されると来て良かったと思うんだけどな、ちぃは判ってたんだな。強引に連れてこさせられたよ」
そんな顔とはどんな顔だろう。自覚が無いだけに恥ずかしい。
「それに当分は、……弄られるだろうな」
そう前を見据えるだいちゃんにつられて前を見遣るが、見なければ良かったと心底後悔する。
ニヤニタと二つの顔が私たちを眺めて何やら楽しそうだ。
「はぁ、先を越されたよねぇ? ちぃ」
「ほんとだねぇ、でもゆーこだって居るじゃないのよ」
「あれはかなり時間掛かるわ、あたしからは告白なんて絶対に無いから、当分は……ねぇ」
「まぁまぁ、その間は少し分けて貰えばいいのだよ」
二つのニタ顔が再び私たちを捉える。
「あのぉ、出来ればそっとしておいて貰えるとあり」
「嫌」「いや」
二人の声が左右の耳にこだまする。
「昼休みはモチロン」
「放課後だって離さないよ?」
どこで打ち合わせをなさったんですか。二人の息がぴったり合っている。
まずは告白シーンから話してもらおうかね、そんな楽しげな相談をするちぃとゆーこ、おろおろとする私、既に観念しているかのように苦笑を絶やさないだいちゃん。
それぞれがそれぞれの道を歩き、しかしこれ程までに近くに感じられる喜び。
親友が居て、好きな人が傍にいる幸せ。
それらを手にしてしまった私は、これからは大変な思いをするのだろう。
どんなに辛い事があろうと、離さず、失わぬように努力しなければならないのだ。
苦にならない努力を努力と言っていいのか分からない。
それでも私は、この関係を壊さぬよう、大切に、しっかりと繋ぎ留めるよう努力を惜しまない。
私は弱い人間だ。
だからと言って甘えてばかりは居られないし、手にした物を手放す理由にはならない。
あの暗闇も、今ここにある光も、私が私である為の要素。
そして何より、傍にいてくれるこの三人こそが、私自身を作る大切な宝物なのかも知れない。
遠くで予鈴の鐘の音が聞こえる。
お互いがお互いを見遣り、意思疎通を交わす。
そして駆け出す私たちは、どこまでも行っても共に在るのだろう。
――みんな足が速いな。
簡単には追付けそうにない速さだ。
それでも走るのを止める訳にはいかないが、既に挫けそうになる私なのだった。
おわり