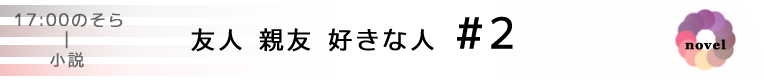五時間目が終了し、六時間目が始まるチャイムと同時に教室へと戻った。
早退しようとも思ったが、あまり良い言い訳が思いつかなかった。それにちぃには散々言われていることだが、私は生真面目なのだろう、嘘を吐いてまで早退する気にはなれなかった。
まだ目元の腫れは目立つが、授業開始直後だったこともあり、クラスメイトには気づかれずに済んでいる。
だいちゃんに酷い事をしてしまった後悔と、遣る瀬無さだけがつのり、ちぃにとっての最愛を傷つけたという事実が、私を苛んでいる。
ずっしりと重く感じるこの気持ちをどう扱って良いのか分からないでいた。
どうしたらいい?
どうしたら私はこの重たい気持ちを捨てることが出来るのだろう。
だいちゃんへの気持ち。そしてちぃへの後ろめたい思い。
その両方を抱えることの出来ない私は、その場で崩れ去り、涙で溺れそうだ。
好きになんかなりたくなかった。だいちゃんへの気持ちになんて気づきたくなかった。そうすればこんな想いも、あんな事もなかったのに。
ちぃには話さなければならない。そして謝らないといけない。
そうしなければ私の気持ちは押し潰され、壊れてしまうような気がする。
六時間目が終わりを告げようとしている。
終わりと同時に声を掛けよう、でなければ決断が鈍ってしまう。
それに時間が経ってしまうと、この気持ちを支え切れなくなってしまうのではないか。そんな不安もある。
チャイムが鳴り、号令がかかる。教室に喧騒であふれるのと同時に、ちぃに声を掛けようとしたが駄目だった。
ちぃの表情が。ちぃの瞳が、今にも泣きそうで、悲しみとも怒りとも言えない表情をしている。
勢いをそがれた私は、声を掛けられないままその場に立ち竦んでしまう。
そんな私に気づいたのか、ちぃがこちらを見遣る。
――話しかけないで。
そんな怒りばかりが込められた瞳で私を睨む。
初めこそ疑問しか湧いてこなかったが、思い当たる事があった。
屋上での出来事。だいちゃんに対してしてしまった私の態度が、ちぃを怒らせたのだろう。
だがふと思う。情報が早すぎやしないかと言うことだ。屋上での一件はついニ、三時間前の出来事なのだ。その場に居合わせた誰かがちぃに伝えたのかも知れないが、それにしたって早過ぎる。
しかし他の理由が見つからない。
私の気持ちを知っての怒りならば分かるが、夕暮れの商店街からというもの、私はちぃと面と向かって会話をしていない。
私自身、自分の気持ちに気づいたのは、つい先ほどなのだ、ちぃが知るはずはない。
他の理由を探してみるが見当がつかない。
私が知らない間に、ちぃを傷つけているのかも知れない。そう思うと怖かった。
原因が分かれば対処は出来る。しかし、その原因が分からないければ、これからもちぃを苦しめる羽目になってしまう。
話さなければ。その原因を聞き出さなければならない。
ちぃは教室を出るところだ、今声を掛けなければ間に合わない。
しかし、動けなかった。ちぃの後ろ姿が先程の表情を思い起こさせ、躊躇ってしまう。
なんて臆病なのだろう。何も出来ず、重たくなってしまった気持ちを抱えたまま、その場に立ち尽くす。
「今日のちぃはどうしたんだろうね。何か知ってる?」
ゆーこが心配そうに声を掛けてくる。
私はどう言っていいのか分からず、曖昧に頷いてしまう。
そんな私の様子に小首を傾げ、戸惑ゆーこ。
「……まぁ、明日になれば何時ものちぃに戻ってるかもね。帰る?」
「……うん」
そうして、私たちは教室を後にし帰ることにした。
その途中、ゆーこに相談してみようかと幾度となく思ったが、出来なかった。
ゆーこには頼れない。逃げ道を作ってしまうのではないかという事と、こんなにも弱い私を見せてしまう事で、呆れられ、嫌われてしまうのではないか。この時の私はそんな馬鹿げたことを真剣に恐れていた。
それに、ゆーこにはちぃの傍にいて欲しかった。
あんなにつらそうなのに、私だけが楽になろうだなんて、到底思えない。
結局、何も相談できずに帰路に着いた。
翌日も空は晴れ渡り、快晴という言葉が当てはまるのだろう。
何時もの待ち合わせ場所にちぃは現れず、ゆーこと共に登校した。
ちぃはホームルーム直後に登校し、何事もなかったように着席するが、休み時間などは昨日と同じように机に突っ伏すため、クラスメイトも声を掛けづらいようだった。
休み時間の度に声を掛けようとするが、それには至っていない。
そして、放課後。
私は意を決し、ちぃを呼び止める。
一緒に帰ろうよ。そんな変哲もない言葉だったろう。それでも私を無視し歩く姿がどうしようもなく私を追い詰めた。
親友に、大好きな友人に無視される事に、どうしたって耐えられる訳が無い。
身近な人にすら、嫌われたくないと臆病になってしまう私なのだ、ちぃに無視される事に、深い絶望を感じる。
このままちぃたちとの関係が終わってしまうのは嫌だ。
それこそ、これからの私の人生が暗いものになってしまう。
引き下がる訳にはいかない。
抗っていれば、今の状況を打開できるヒントが見つかるかも知れない。
そんな希望だけが、今の私の支えだった。
ただ一緒に帰りたい。それだけでは駄目だ。
「ちぃ。話があるの……。だいちゃんの事で大切な話なの」
そんな決意を口にしても駄目だった。
昇降口を出ても尚、私は食い下がったが、その勢いも次第に弱くなってゆく。
立ち止まるどころか、私すら見てくれない事に、心が痛み出す。
そして諦めかけた時だ。ちぃはそのまま校庭を突っ切り校門へと向かうものだと思ったが、道を逸れる。
ふと弱りだした気持ちが、調子を取り戻す。
校舎裏だ。
小さい裏門が遠くに見え、その先には園芸部が所有する温室や旧部室棟が見える。
「なに?」
立ち止まり、私を一瞥するちぃは、昨日と同じ表情をしていた。
怖い。それでもこのままの関係が続く方がもっと嫌だった。
息を深く吸い込み、力を入れる。
「ちぃ。ごめんなさい。私はだいちゃんを傷つけた。だいちゃんに酷い事をしたの」
精一杯の謝罪をし、ちぃの怒りの原因を聞き出さなければならない。
しかし、思わぬちぃの態度に原因が明らかになる。
「それが?」
それがどうしたと、ちぃは嘲笑と共に吐き捨てる。
「何? わたしに惚気でも聞かせたいわけ? ……帰る」
「待って! 惚気って、どうしてそうなるの」
「わたし知ってるよ。だいちゃんの気持ち。それにあなたの気持ちだって知ってる」
愕然とする。
あの日、商店街での一件からちぃの様子はおかしかった。
しかしそれは自身の気持ちに気づき、どうしたら良いのか分からない、そういった落ち込みようだと思っていた。
だからこそ、私の気持ちを知られる前に、だいちゃんから距離を置こうと決めたのだ。
だけど遅かった。何時から私の気持ちに気づいたのだろう。
私が私の気持ちに気づく前から、ちぃは知っていたのだろうか。
「喧嘩するほど仲が良いんだね。羨ましい限りだよ。でも、最低だね」
そう言って私を睨みつけるちぃは、今までに見せたことのない憎悪を含んでいる。
「わたしの気持ちを知っていながら、惚気ようとするなんてね。あなたってそういう人だったんだ」
「ちが……」
「違う? どこが間違ってるのよ。だいちゃんはあなたが好き。あなたもだいちゃんが好き。それをあなたは自慢しに来たんでしょ? それとも何? わたしが目障りだから消えろとでも言う……」
「違う!!」
そんなこと無い、そんなこと思う筈がない。
私はちぃを睨みつけようとしたが、ちぃの表情を見てうろたえてしまう。
「なにが違うんだよ。……何が! 違うって言うんだよ!!」
涙を目尻一杯に溜め、訴えてくる。
わたしも好きなのだと。わたしもだいちゃんがこれ以上なく大好きなのだと、そう伝えてくる。
「でも叶わないじゃない。わたしはこの想いをこの感情をどうしたらいいの? 上げることも、表に出すことすら許されないのに。わたしに、どうしろっていうのよ!」
私の願いは、ただの我侭なのだろうか。
みんなと一緒に居たい。それだけの願いは叶わないものなのだろうか。
「もういいでしょ。帰る」
そう言ってその場を後にする。
その背中を引き止めることも、声を掛けることすら出来なかった。
大丈夫だと。私は諦めることができるから、安心していいと。そう言えば良かった。
でも、伝えることは出来なかった。
それは私自身、諦めたくないと言っているようなものだ。
もうどうにも出来ないのだろうか。
私はその場に立ち尽くし、ただ涙を流すことしか出来なかった。
自室のベッドで横になる。
気づいた時には玄関の前で、どのような経路で帰ってきたのか全く思い出せない。
どうしてこうなってしまったのだろう。
だいちゃんに対して酷い事をしてしまった事。ちぃに対して何も言い返せなかった事。そんな事を永遠と考え続ける。
四人が自然と集まり、気兼ねなく傍に居られて、たまにだいちゃんとちぃを持てはやしたりして、そんな楽しい時間を過ごせたらいいと思っていた。
私が勝手に望んでいた事だが、これだけは譲ることは出来ない。その為にはやはり、この気持ちが邪魔だった。
だいちゃんへの想い。
こんなもの捨ててしまいたい。捨ててしまわないといけない。
しかし、どうしても出来そうにないのだ。
あの声も、あの表情も、あの仕草も、全てを無視することなんて出来ない。
屋上での一件を思い出すたびに、後悔の念が押し寄せる。
今の私には必要のない感情。
しかし嫌われたくないと思う気持ちが私の邪魔をする。
ちぃには笑っていて欲しい。涙なんかこれっぽっちも似合わないのだから。そう願えば願うほど、私の気持ちも押し潰される。
私がいる限り叶わない願い。
私が傍に居るからこそ、ちぃは涙を流し、苦しんでしまう。
だいちゃんの気持ちは私に向いているのだ。
それはまやかしだと、忘れて欲しいと言ったところで、だいちゃんの気持ちはだいちゃんのモノだ。どうすることも出来ない。
なんて残酷なのだろう。今のこの状況がこれ程憎く思えることはない。
私が存在することによって、以前の関係に戻ることが出来ない事実。
私が傍にいるから、ちぃは苦しみ、だいちゃんまでも傷つけてしまうのだろう。
涙は止まらない。
次第に世界の色が薄くなり、存在が危うくなってゆく。
私を取り巻く環境、私が存在し関わっている事柄、その全てが敵のように思えてくる。
私に抗う力もなければ、武器もない。
このままでは駄目なのは分かっている。しかし、抵抗する力は私には持ちあわせていない。
――もう、どうでもいいや。
全てを捨ててしまえばいい。
関わろうとするから駄目なんだ。
涙を流すことに、悩む事にも疲れた。
その倦怠感と共に湧き上がる感情が、恐ろしモノに感じる。
もう戻らないのなら壊してしまおう。そんな事をしても意味が無いことは理解していたが、その考えを訂正する友人も、気持ちも、感情すら、今の私には存在しない。
だいちゃんが私に向ける気持ちだけは、どうにか壊してしまわなければならない。
それがちぃに対して私が出来る罪滅しだ。
今日の空は暗かった。
いや晴天と言っていいが、明るさが微塵も感じられない。
全ての物がどうでもよく、全ての事柄に無関心だった。
登校途中、ゆーこに声を掛けられ、何時もと変わらない挨拶をされたが、今の気分は最悪で鬱陶しく思えた。
教室ではクラスメイトで作る喧騒が、私を影へと追いやる。
ちぃの様子も相変わらずだった。
それに関してだけは思い当たることがあった。
もう少しの辛抱だよ。
そう励ましながらも、同情という言葉がしっくり来るだろうか、そんな哀れみを惜しみなくぶつけてやりたい気持ちになった。
そして昼休み。
ゆーこはちぃと共に教室を後にした。
その事に少なからず安堵する。
今日は独りで居たい気分だったし、やはりちぃの傍に居てあげて欲しいかった。
ふと自嘲がもれる。
思いやる気持ちが未だに残っていることにだ。
今朝から私の心の中は静寂の一言に尽きる。感情の全てが欠落したのではないかと思えるほどに静かだ。
関心も感動もない。ただここにあるのは憎悪と呼べるものなのだろうか。言いようのない真っ暗闇だけが存在している。
どこにも行く気にはなれず、自分の席でお弁当を広げているとだいちゃんが声を掛けてきた。
こればかりは素晴らしいタイミングだと思った。
放課後にその胸の内にある物を叩き潰してやろうと思っていたが、こんなに早くに叶うなんて思いもしなかったからだ。
屋上へと移動する。
だいちゃんを苦しめる定番の場所となりそうだと、内心ほくそ笑む。
「なに?」
そう鬱陶しそうに訊ね、だいちゃんはぽつぽつと話し始める。
しかし私はだいちゃんの話には全く興味が沸かなかった。
何かを謝罪しているみたいだが、その全てが右から左へと流れる。
だいちゃんへの想いは、存外、簡単に捨てることが出来たのだろう。
真面目な、少し困ったような表情をしているが何も感じない。
逆に何故そんなに一生懸命なのかが知りたかった。
つい最近、あんな拒絶をして見せても尚、何かにすがっている。
私に関しては、何を言っても、何をやっても無駄だというのに。
そこではたと気づく。
私はまだ伝えていない。この胸の内にあるドス黒い物を見せていないのだ。
そして未だにあるだろう、私への想いを潰していない。
だからこそ、こんなにも一生懸命になれるのだ。
私も持っていたが捨ててしまった。
あの明るい世界に何かを求め、願い続けたこともある。
しかし、それら全ては無駄だったのだ。カタチ有るモノはいつかコワレル。
気持ちにも、関係にも、瞳に映らない全ての事柄に、カタチは存在している。
その事を今回の事で実感した。
「……嫌い」
「え、なに?」
急な言葉に驚くだいちゃんは無防備だった。
今なら分かる気がする。
だいちゃんの中にある想いがカタチを成し、手にすることが出来るような気がする。
それを手に取り、握り潰してみた。
「全部あんたの所為よ」
それでも駄目なら、地面に叩き付け、踏みにじる。
「私は、あんたが大っ嫌いよ」
壊れろ。壊れてしまえ。こんな気持ち、私には必要ない。
「全部あんたの所為なのよ! あんたを見てると苛立つわ。これからは私に話しかけないで」
この世界で叶うものなんて何一つ無い。
傷つき、傷つけられ、傷つける。こんな事しか出来ない世界に、なんの価値がある。
「それじゃあね。二度と近づかないで」
後悔や罪悪感、そんなものは今の私には十分過ぎるほどだったからだろうか。
何も感じず、思いもしなかった。
去り際、だいちゃんは私に叫んでいたのだが、振り返る気力もなく、その場を後にする。
階段、廊下、教室。
全ての場所に喧騒が溢れるこの時間。
私の中だけは静寂が取り巻いている。
その静寂が治まり、慌しくなる日はもうないのだろう。そんな予感と、希望だけが私の支えだった。
静かな場所は元々好きだったのだ。
それがこの学校に通うようになってから、ずっと騒々しかった。
親友と戯れ、好きな人を想っていた時間は、永遠に得られないくても良い。
ただ慌しく、最後には燃え尽きてしまうのだから、そんなモノ、私はもう欲したりはしない。
こんなにも黒く、何も見えない程に暗くなってしまうのなら、私には必要ない。
この世界は真っ暗だ。
何もかもが色褪せ、興味を惹かれない。
それでもいい。
あんな想いをするくらいなら、初めからこの世界にいればよかったのだ。
そうすれば、苦も無く、私は生きられたのだろう。
慣れるまでは、暫し辛いこともあろうが、これまでの事を思うと耐えられる。
それに慣れなければならない。
私はこの暗闇で生きてゆくしか無いのだから。
授業に集中できた所為だろう、午後の授業はあっという間だった。
どんな心境だろうと、私は学生なのだ、勉強しなければならない。
悩むことを放棄してしまった私は、授業内容を頭に詰め込む作業が楽に感じ、無駄な思考を使わなくて済んでいる為か、割かし簡単に理解もできた。
そして放課後、帰ろうとする私の手を強引に引っ張る者が居た。
ゆーこだ。
私を睨みつけ、どこかへ誘おうとしている。
その行為が、その表情が鬱陶しく思い、私は拒絶しようとする。
「なに。私帰るんだけど」
しかし私の言葉には耳を貸さず、人気のない廊下へと連れていかれる。
ゆーこは知っているのだろう。
人望に厚いゆーこは様々なタイプの相談を受けているらしい。その代償として、意に介さず情報も集まってくる。ここ最近の私に起こったことも承知済みなのかもしれない。
だからと言ってどうするつもりなのか。
私の中を支配する静寂を押し付けがましい好意によって、消そうとでも言うのだろうか。
やめて欲しい。
私が選び、決断した選択だ。誰にも邪魔はして欲しくなかった。
「あんた、ここに連れてこられた理由。分かる?」
「分からないし、知りたくもない」
邪魔はして欲しくない。
ゆーこだけは私の気持ちを察して、放っておいて欲しかった。
私はこれから、拒絶しなければならない。
ちぃとも、だいちゃんとも一緒に居れないのだから、ゆーことも距離を置くべきだ。
結果的にゆーこを傷つけてしまっても、今の私には関係ない。
「ゆーこ。丁度いいから言っておく。もう私に関わらないで」
今更、人を傷つける事に抵抗もないようだった。
それが親友であろうとも、既に経験済みだし、痛みも知っている。
それに好きだった人すらも傷つけた事があるのだ、怖いモノなんて無い。
「お礼だけ言っておくよ。今までありがとう。これからは」
急に視界が揺れる。それと同時に右頬が熱を持ち、痛みだす。
叩かれたのだ。
驚いたものの、怒りも何も湧いてこない。
「用は済んだ? 帰るよ」
踵を返そうとした時、何かがぶち当たる音と共に、先程とは比にならない痛みが右頬を襲う。
おもいっきり叩かれた。
その衝撃と共に、ゆーこを睨みつけるが、私の身体は動けなくなる。
何故、そんなに痛そうな表情をしているのか。
何故、涙を堪え、打ち震えているのか。
叩かれたのは私だ。それなのにどうしてゆーこがそんなに痛そうにしているのか分からない。
そして、何かが私の中で弾ける。
直ぐに消えてしまった感情を私はどうすることも出来ずに、見過ごした。
「どうして殴られたのか分かる?」
嫌だ。知りたくない。
先程私の中で弾けた物が気になるが、今の私には必要ないものだ。いや、有ってはならないものだ。
「わから……」
「分からない訳、ないでしょ。言ってみなよ。あんたはどうしてあたしに殴られないとならないの?」
また何かが弾けた。
その数が次第に増え、私の静寂が、少しずつ崩れ落ちてゆく。
好きでもないが居心地は良かったのだ。
崩されてたまるか。
「分からないよ。叩かれたことは別に気にしないから」
帰らせて。その言葉が出なかった。
私の胸ぐらを掴むゆーこはより一層、眉間に皺を寄せている。
「だったら教えてあげるわ。あんた、親友をなんだと思ってるのよ」
親友? そんなもの、何時かは壊れてしまう尊い関係だ。
私は欲しくない。こんな思いをするくらいなら最初から居ない方がましだ。
「聞いてるの? あんたは親友を」
「親友? 親友なんて直ぐに壊れてしまう、ただの友人でしょ?」
驚くゆーこは奥歯を噛み締め、より一層険しい表情になる。
「何か間違ってる?」
「えぇ。だからそんな態度が取れるのかと、納得したわ。それと同時に、なんて哀れなんでしょうね。あんたに同情するわよ」
静寂が少しずつ戻ってくる。
まだ騒がしさは多少残っているが、どうにか出来そうだ。
「なに? 同情したいが為に私をここに連れてきたの。なんて偽善者だろうね。反吐がでるわ」
「そう。で? あんた、あんな事してこれからどうするつもり?」
「あんなこと? 見当がつき過ぎてどれを言っているのか」
「だいちゃんにしたことよ!! あんた、あんな態度して後悔しても……」
ふと、何かが私の中に入ってきている。
何かは分からないが、取り戻そうとしている静寂が、また乱れ始める。
「後悔? 後悔なんてずっと前からしてるよ!! でも、もうどう仕様も無い。私にはどうすることも……」
出来ない。
俯きそうになる視線が釘付けになる。
ゆーこの涙がはっきりと見える。
ただの偽善者だ。目の前にいるのは自身の欲求を叶えたいが為の、ただの傲慢な人間だ。
そう自身に言い聞かせようとするが、音が邪魔をする。
静寂の中に、微かに聞こえていた弾ける音が、より一層強くなる。
「どうして相談してくれなかったの」
いやだ。聞きたくない。聞いてはならない!
「どうして、そうなる前に! あたしに相談してくれなかったのよ!!」
「出来るわけが」
「無いというの? 本当にあたしはただの友人だったの?」
心の中が五月蝿すぎて肯定する言葉も、首を縦に振ることも出来なかった。
「じゃあどうして!」
弾けて消える。
「出来るわけがないだろ! ちぃを一人になんてしたくなかった。ゆーこが私なんかに構っていたら、ちぃは独りで苦しむ羽目になるじゃない」
静寂が消えてゆく。
「それに、逃げ道を作るようで怖かった。こんなに弱い私を見て、嫌われてしまうんじゃないかと思うと、相談なんて出来なかった」
「あんた、馬鹿だよ」
「……」
「どうして嫌う要素があるのよ。どうして逃げ道になってしまうのよ。今のあんたは逃げているとは言えないの? 独りになろうとしているあんたは、弱い者だと言えない?」
やめて。もう戻りたくない、あんなに苦しく、痛みを持つ世界になんて戻りたくない!
「戦いなさいよ。ちぃとも、だいちゃんとも。あんたが自分を弱い人間だと言うのなら、あたしが見方になるわよ」
一筋の光が私の中を執拗に照らし出す。
「それでも、あたしと一緒に居るのは嫌なの?」
抗うことも、拒絶することも、今の私には出来そうになかった。
先程から弾けていた物。それがなんであったのか理解する。
後悔だ。
そしてその後悔する気持ちがこれ以上無いほどに私を襲う。
「もう、ダメだよ。私は二人に酷い事をしたんだ。もう後戻りは出来ない」
あれ以来流れなかった涙がこぼれ始める。
この涙は嫌いだ。悔しさと後悔しか感じることの出来ない、この涙は大っ嫌いだ。
もう泣きたくないのに、もう考えても仕様のないことなのに、静寂が戻ってこない。
いやだ。
あの眩しく尊い時間に戻りたい。みんなの笑顔の傍に居たい。そんな事ばかりが私の中を支配する。
「まだ大丈夫。謝れば許してもらえるよ」
「だめよ!」
許してもらえたところで現状は変わらない。私がちぃの邪魔をしているのは明らかなのだ。
ちぃにとっては、今の状況の方が良い結果になるはずだ。
私はちぃの邪魔をしたくはない。
「私は、みんなの傍には居られない」
「どうして」
「……ちぃの邪魔をしているのは私なんだ。それにだいちゃん……。だいちゃんにも酷いことをした」
ゆーこは目を見開くがそれは一瞬のことで、すぐに溜息を漏らし、私を見遣る。
「それでなに? あたしたちから距離を置こうって?」
「だって、私がいるから二人は」
あからさまな溜息に遮られる。
「あんた、自分が悲劇のヒロインとか思ってるんじゃないでしょうね? あ、逆か。あんたから見たらちぃがヒロインになる訳だ。そしてあんたは邪魔をする恋敵か。それに気づいたあんたは、あたしたちから逃げようってか? ……馬鹿じゃないの?」
馬鹿、なのかもしれない。
だからこそ私なりに、ちぃを思いやった行動をしてきたつもりだ。
「あなたはだいちゃんの事、好きなんでしょ?」
「……好きじゃない。私はだいちゃんを友達以上になんて見れない」
「またそんな嘘を」
「嘘を……、嘘をついて何が悪いの? 私はちぃの邪魔をしたくない! 私がだいちゃんを好きにならなければいい事かもしれない、でも。……でも、どうしようもないんだよ! 私にはこの気持ちを殺す事なんて出来ない! 出来そうもないんだよ!!」
後悔と共に感じていた強い感情。
傍にいたい。あの笑顔の傍で笑っていたい。
だいちゃんを想う気持ちが、どこに隠れていたのだろう。私を責め立てていた。
「なんで殺す必要があるのよ」
「だって、それじゃあちぃが!」
「……あんた、その考え間違ってるとは思わないの?」
何が間違っていると言うのだ。
私が苦しんでいること自体が間違いだと言わんばかりに、ゆーこは溜息を吐く。
「ちぃは関係ないでしょ? あなたがどうしたいかよ」
「関係ない?」
「そうよ。ちぃもあなたもだいちゃんが好き。だからってあなたが気にしても仕方が無いわ。ちぃは関係ない。あなたがどうしたいのか、それだけでしょ?」
「それだけ? それだけって何? ちぃが関係ないわけないだろ!! たぶんちぃはずっと昔からだいちゃんが好きで、最近やっとその気持ちに気が付いて、これからって時なのに……、どうして関係ないなんて言えるんだよ!」
「……それで? だから今回はちぃに譲ってあげようって訳?」
譲る? 譲るってなに?
「あんたは優しいねぇ。いや、違うか。勝者の余裕ってやつ?」
「違う!! そんな、そんなこと思ってない!」
「じゃあなに? だいちゃんに好きでもない相手と付き合わすのが、あんたの趣味なわけ?」
「好きじゃない訳がない! あの二人はあんなに息が合っていて、お似合いなのに。私なんかが現れた所為で」
急に視界からゆーこが居なくなる。いや、また叩かれたのだ。同じ右頬を。
「あたし。初めて人を殴ったよ。でもあんたが初めてで良かったわ、それがどうしてか分かる?」
分からない。分かる筈がない!
「あんたが親友だからよ。なんの気兼ねもなく殴れるわ、これからもずっとよ。そしてもし、これから同じ人を好きになってしまったら、あたしは躊躇いなくあんたを蹴り落とす覚悟を持てるわ」
親友だから。
「そんなの」
「親友じゃないって言うの? あんたの言う親友って何? 全てを譲り合うのが親友なの? あなたが先に好きになったのだからって身を引くのが親友なの? そんな気を遣いあう関係なんて果たして親友と呼べる? 違うでしょ? 気兼ねなく傍に居られるのが親友じゃないの? ライバルにもなれる、そんな関係が親友と呼べるものだと、あたしは思っているけど。違う?」
それが親友?
「それにね。あなたを心から信じているからこそ出来るのよ。もし同じ人を好きになって、その人があなたを選んだってあたしは納得するし、安心するわ。諦めもつくのよ。逆にあたしが選ばれたのなら、心置きなくその人と付き合うわよ? あなたなら他にいい人見つけ出せると思うだろうし、その失恋から立ち直れる力を持っていると信じている」
「そんなこと」
「無い? 確かに、今回の事であなたの弱さを教えてもらった。でもね、だからこそ信じられることもあるのよ。幸運な事にあたしたちは三人よ。どうしても一人では耐えられない時は、ちぃと好きなだけあたしの悪口を言えばいいわ。その逆も然りだけどね」
どうかしら? そう私の瞳を覗き込み問うてくる。
「違うというのなら、残念だけどあんたとは親友になれないかもね」
「そんな人……」
「今まで居なかった? だったら、あたしたちが親友になってあげる。ん、違うね。親友になろうよ。これから少しずつさ」
そう言って微笑むゆーこはこれ以上ないほどに力強く、そして頼もしく見えた。
頬の痛みの所為か、それともゆーこの優しさの所為なのか。
涙が止まらず視界が歪んでゆく。
俯く私を優しく抱きしめるゆーこからは、落ち着く香りがした。
「あんたって泣き虫なんだね。ずうっと泣き通しだったんじゃない?」
辛かった?
うん。
そらそうでしょう。一人で抱え込んでたんだもん。
うん。
だからね。
「あんたから相談されるのをずぅーーーーーっと待っていたあたしに一言ない? 正直これが本題だったんだよ。除け者扱いだし、相談してくれないから親友と思われてないんだなって感じて、悲しかったわ」
「……ごめん。本当に、ごめんなさい」
ゆーこの胸の中で泣きじゃくる。これほど恥ずかしいこともなく、これほど落ち着くこともなかった。
「こんな事になったのは、それも一つの原因ではあるのよ? まぁ、結果的にあんたを殴れたから良かったけど」
「それ、変な意味にしか聞こえない。……だけど私も殴られて良かったかも」
「あんた……。エムの人だったの?」
じゃあ、ゆーこはエスの人だったんだね。そう言って笑いあう。
久しぶりに笑った気がした。
ほんのささやかな、微笑み程度の笑いだったけれど、とても心地がいい。
しかし不安が消えたわけではない。
「これからどうしたら良いんだろう」
「そんなの自分で考えな。大切なのはあんたがどうしたいのか、だよ」
ゆーこさん。相談して欲しかったと言うわりには、全く助言を貰えていない気がします。
私にちぃを蹴り落とす勇気なんて持ち合わせていない。
それにみんなと離れたくない気持ちが一層強くなる。
「さて。次はヒロインとの戦いだね」
え?
「ちぃに会っておいで」
そう言って背中を押される。
振り返り、今だ涙で霞むゆーこを見遣る。
不安で仕方がない、何をどう話せばいいのかも分からない。どんな顔をしてちぃに会えば良いのか分からない。
それなのにゆーこはこう言ってくる。
……甘えるな。だけど今回は甘えて来い。
そしてもう一つの助言。
私自身がどうしたいのかという事。
それは、全てを諦め投げ出すことじゃない。欲しい物をどのようにして手に入れるかという事だ。
泣き腫らしたままの顔で、私は学校を後にする。
恐怖と不安しか存在しない感情。
色を失いかけ、しかし、ほんの少しだけ色の付いたこの世界。
正直、怖い。
またあの苦しみを味わうことに、どう仕様も無い恐れがある。
しかし、それと同時にもう一つの感覚が残っている。
安堵感だ。
ゆーこが、親友が居るという事実に安堵している私は、恐怖があっても前へ進める気がした。
傍に感じれるだけでいい。
独りしか居ないあの静寂が、今では恐ろしいもの感じる。
ちぃは今どうしているのだろう。
早く会いたい気持ちが自然と湧いてくる。
静寂が一掃し、私の心の中はまた慌しくなる。つらい事も、苦しい事もある。しかし、代えがたい大切な事もある。
前者の方が多いのかもしれない。
しかし後者のそれらは、苦しい事に耐えられる特別なモノなのだ。
空を見上げる。
あれほど暗かった空は、今では眩しい位に輝いている。
信じる心。
それを携え、私はちぃの元へと向かった。
学校からの道のりが、存外長く感じた。
武家屋敷を何度か改装したのだろう。和風と洋風とがほんの少しミスマッチだ。
そんなちぃの家の門前。私は吐息をつき、気合を入れようとするが、何に対して意気込めば良いの分からず立ち尽くしてしまう。
私はちぃに会って何を話せばいいのだろう。
私の気持ちを伝えなければならないのは分かる。しかしその後は? 宣戦布告でもすればいいのだろうか。
ふとゆーこの言葉が思い起こされる。
……あなたがどうしたいのか。
その言葉はちぃにも当てはまる。
ちぃは何を考え、どうしたいと思っているのだろう。
ちぃの考えていることが分からない以上、対処方も何も思いつかない。
それこそ、私がだいちゃんを拒絶した時のような事が起こった場合、私はどうすることも出来ないのだろう。
そう考えると不安が増す。
もうちぃの涙は見たくない。
そして何より、一緒に居れない事にでもなったら、私は耐えられそうにない。
恐怖に苛まれてしまう。
私はちぃの事を何も理解していなかった。知ったような気になっていただけだ。
どうしようも無い時は、やはりだいちゃんへのこの気持ちを捨てるしか無い。
ゆーこの話では取り合いも出来るからこそ親友だと言っていたが、今の私にはやはり無理なのかもしれない。どうしても親友の幸福を考えてしまう。
それに、ちぃには嫌われたくない。
私が我慢するだけでそれが叶うのならば、やはり私は……。
そんな感慨が苦笑と共に一瞬にして消える。
私はゆーこになんと言っていた? このだいちゃんへの気持ちは、そう簡単に引き下がらないと豪語したのではなかったか。
頬が熱くなる。無我夢中だったにしろ、あれは赤面物の台詞だ。
戦おう。
正面からぶつかり合うことを戦いと言うのならそうなのだろう。
少し違う気もするが、どの道ちぃとは話し合わなければ始まらないのだ。
戦って、競い合って、お互いを認められたのならいい。
逃げず、隠さず、私という人間を見てもらい、そして共に歩いていきたい。
どうにかなる。いや、どうにかしてみせる。
意を決し、呼び鈴に手を伸ばすのと同時だ。引き戸式の扉ががらりと開く。
「遅い!!」
ビクつき唖然とする私と、不意を突かれたちぃとが顔を付き合わせる。
何が遅いのだろうか。何か荷物でも届く予定があるのかな。まぁ、そういった宅配便などは意に介さず遅く感じるものだが、しかし、表に出てきて叫ぶほどのことだろうか。
そんな事を考えるくらいの時間が流れ、不意にちぃは空を見上げこう告げる。
「遅くない!!」
しかし直ぐに落胆の色を見せ、私を睨むがそれは見知った、されど久しく感じるじゃれ合う時の表情だ。
「……タイミング悪すぎ」
「ご、ごめん」
反射的に謝ってしまうが、何に対して謝罪したのかいまいち掴めていない。
「とりあえず入って」
玄関へと姿を消すちぃの後をゆっくりと、だけどしっかりとした足取りでついて行く。
玄関で靴を脱ぎ、そのまま中庭が見える廊下を歩く。その突き当たりにある階段を上り、一番奥に見える扉がちぃの部屋だ。
その部屋に通され、何時もの場所にクッションを用意してくれるちぃは、お茶を持ってくると言って、一旦部屋から出て行った。
辺りを見渡す。分かり栄えのしない部屋だが、可愛らしいぬいぐるみがちらほらと見受けられる。そんな女の子な部屋の様子をしている。
ここまでお互いに無言だったのだが、私は決して臆しているわけではない。
逆に今ではちぃと正面からぶつかりたいとも思っているのだ。
私を知って欲しいし、ちぃを知りたいと思っている。
大丈夫だ。ゆーこに貰ったこの気持ちがあれば、ちぃとだってうまくいく。
ゆーこには感謝しなければいけない。私を立ち上がらせ、勇気をくれたのだ。ゆーこにはお返しをしなければならない。
何が良いかと考えている時にちぃが戻ってきた。
お互いにお茶を一口含み、落ち着いたところでちぃから切り出してくる。
「さて、とりあえずその左頬をわたしに差し出しなさい」
……はい?
未だにヒリヒリする右頬を押さえ首を傾げる。今気づいたが少し腫れているようだ。
そんな呆けた態度にちぃは憤慨する。
「だってその右頬はゆーこがやったんでしょ? だったらわたしは左頬を貰ってもいいと思うの。丁度わたしは右利きだし好都合でしょ?」
理解しがたいが、どうだろう。上げてしまっても良いのだが、それにどんな意味があるのかが分からなかった。
殴り合える仲こそ、ちぃの考える親友なのだろうか。
ちぃが私に迫ってくる。
その表情には、どこか言いようのない暗い微笑を浮かべている。
「準備はいい?」
そう尋ねてくるちぃは、何とも言えない威圧感があった。
「ああの、ちょっと待って。まだ何も話してないのになんでそんあ」
逡巡するようにちぃはそのまま呆けてしまうのだが、直ぐに落胆し、その場に座り込んでしまう。
「全部。あなたが悪い」
その言葉に背筋が凍りつく。
やはり私は、ちぃに怨まれるような事をしていたのだ。
私のだいちゃんへの想いがちぃを傷つけているのだろう。
大切で大好きな人を取られてしまう恐怖。今の私なら理解できるような気がする。
私は耐えられる自信がない。ちぃならば許せると考えていた時もあるが、やはり心の片隅に残してしまうかもしれない。
怖くてちぃを見ることが出来ない私は、本当に臆病者なのだと実感する。
「本当はあなたがこの部屋に入った瞬間に、そのやわっこい左頬を頂いてさ」
――ん?
「何やかんやと説教をして、最後はガシ!! っと抱き合うのを想定していたのに……」
思わぬ会話の流れに、疑問を持ち、素直に顔を上げることが出来た。
私を睨んではいるが、穏やかな雰囲気があり、それこそ拗ねた子供の様子にしか見えない。
「あ、あの……、なんのはなし?」
「だからぁ! 何この青春!! 素敵じゃない?! っていうシーンを想定してたの。それなのにあんな締まらない登場しちゃってさ」
タイミング悪すぎだよ! そう怒りをあらわにするちぃは、クッションをバフンと床に叩きつける。
しかし何だろうこの雰囲気は。これから何かが起こる気配が全く無い。
逆に何時ものちぃが私の目の前に居る。
あの商店街での出来事からの態度が、無かったことの様に思い私は混乱してしまう。
「ちちょっと待って。どう言う事? チャンスとか想定していたとか何の話?」
キョトンと私を見つめ返すちぃだったが、微笑み、穏やかな表情へと変わる。
「まぁ気にしないで」
と言われましても……。
「では、話しを聞こうか」
微笑をそのままにそう尋ねてくる。
突然の振りに動揺してしまい、どのように話してよいのかを考えていなかった事に気づき、少しの間考え込んでしまう。
やはり、自身の気持ちだけは明確にしておかなくてはならない。ちぃは既に私の気持ちを知っているが、私の言葉からそれを伝えなければいけない気がする。
そして、ちぃの気持ちを確認するのだ。
そこからは……。なるようになる!
「わ、私は……」
「わたしは?」
赤面してしまう。そんな状況では無い事は重々承知しているつもりだが仕方がない。
「私は、だいちゃんのことが好きなの。でも……」
ちぃの気持ちも理解しているつもり。そう言葉を紡ごうとしたのだが、ちぃの態度に疑問を持ち、言葉が途切れる。
どこか達観した表情であさっての方を見遣るちぃ。そんなちぃの考えが読めず、とりあえず確かめて置かねばならない事を問うてみる。
「ちぃも、だいちゃんの事が好きなんだよね?」
目を見開き驚くちぃだが、それは一瞬のことで、意に反して満面の笑みでこう告げる。
「うん。大好きだよ? 昔も今もずぅっと」
にへらと、照れ笑いを私に向けてくる。宝物を共有するかのような、そんな嬉しそうな表情を臆面もなく湛えている。
校舎裏でのちぃとは、全くの別人っぷりに少々驚いてしまう。
しかし、そんなちぃを見ていると実感してしまう。こんなに素直な親友を悲しませたくない。
ゆーこに諭され、自身にも言い聞かせたのだが、その意思が次第に弱まり、身を引くこと以外の選択肢しか想像できなくなってしまう。
「やっぱり私は……」
「それは違う」
優しく穏やかな口調。しかし譲る気のない真っ直ぐな言葉。
「わたしに気を使ってだいちゃんを諦める? それは間違った選択だよ」
「それじゃあ奪い合うことになるの? 私は嫌だ。ちぃとそんな関係にはなりたくない」
戦うと。競い合うと決意してここに来たがやはりそんな事出来ない。
「奪い合うって……。まぁそれもいいけどさ。……だいちゃんの気持ち、知ってる?」
「……」
「もう決まっているじゃない。だいちゃんと付き合っちゃいなよ。あいつはなかなかにいい男だよ? 幼馴染のお墨付き」
「それじゃあちぃが……」
「わたしのことは大丈夫。全く気にしないでおーけーだよ」
違う。……違う!!
それでは今までの私と一緒だ。自身の気持ちを殺すことがどれだけ辛いことか。
「それこそ間違ってる! ちぃは我慢できるの? その気持ちを押さえ込むなんて出来るの?」
「わたしはもう慣れっこになっちゃったから」
「そんなの慣れる訳ない!」
目を見開き驚くちぃ。そんなに間違ったことは言っていないつもりだ。
自身の気持ちを擦り切れるまで引き摺る行為に慣れる筈がない。辛いものは辛い筈だ。
「そうだね。ごめん……。でもね、もう決まった事にとやかく言ってもね」
「どうして? 私さえ身を引けばちぃにだって」
「それは間違ってるよ? それとも、だいちゃんを振りたい訳?」
戸惑、言葉が出てこない。
そんな事したくない。屋上での一件でその思いはとても強い。一度振った事になるのだろうが、あんな経験二度としたいとは思わない。
「あなたは、どうしたいの?」
ゆーこに言われた台詞をちぃにも言われ混乱する。
どうしたいのだろう。
お互いに同じ人が好きで、競い合って奪い合うとしたら、具体的にどのようにして結果を出す?
それは対象となる者に委ねるのだろうが、それまでの過程が想像できない。
対象者の気を引くのに一生懸命になるのだろうが、そんな関係を私は望んでいるのだろうか。
「奪い合うって言ったって、だいちゃんの気持ちは決まってるんだよ? それともわたしに略奪愛をしろと求めるの? それだけは嫌。そうまでして手に入れたとしても、長くは続かないとわたしは思うな」
ふと疑問に思う。
なんでそんなに穏やかなのだろうと。恋敵が目の前にいると言うのに、どうしてそんなに冷静でいられるのだろう。
校舎裏でのちぃが幻か何かに思えてしまう。
「? どうしてこんな物腰なのかって顔してるね。話せば長いんだけど……、いいかな?」
そう言って話し始めたちぃは、どこか楽しそうで、種明かしをするように得意げな表情をしていた。
最初にちぃが気づいたのはだいちゃんの気持ちだった。家族のように毎日顔を合わせていれば、自然と知れることだとちぃは楽しそうに話す。
だいちゃんに向ける私の気持ちに気づいたのもその頃だという。
そこでちぃは行動を起こす。
私にだいちゃんの良いところを今以上に知ってもらおうと、アピールし始めたのだ。その気持ちに気づいて欲しいと願いながらの行動だったらしい。
好きな人の話をすると、自然に顔が綻んでしまうのは仕方がなかったという。
そして私が自分の気持ちを自覚した頃に、そっと背中を押してやるつもりだった。
しかし誤算が生じる。
商店街での一件だ。
「ごめんね。あれさえなければ、こんな事にはならなかったかもだけど、わたし自身驚いたんだ」
ちぃ自身、抑えきれなかったらしい。
自分の気持ちは隠したまま事を進めたかったのだが、その出来事によって隠し通せるか不安だったのだ。ちぃは知らないだろうがあの一件が無くても、私はちぃの気持ちに気付いていたのだけど、それは言わないでおいた。ちぃも隠し事は苦手らしい。
しかし、そんな事とはつい知れず、ゆーこに相談することにしたのだ。
こんな事を言うとゆーこが悲しむかもしれないが、第三者としての目が必要になったとちぃは話す。
現状を説明した際にやはり聞かれたらしい。あなたの気持ちはどうなるの? と。しかしこの話題はまた別の話だそうだ。
そのまま何事も無かったかの様にし、今まで通りにすることも出来たのだが、ゆーこはそれに賛成しなかった。
あたしたちはまだお互いを理解しあえていない。これは好機なのではないか。そう言ってちぃにある作戦を持ちかける。
そう。三角関係を演出しようじゃないか。その方が盛り上がるし、修羅場だからこそ見えるものも在るのではないか。そうゆーこは提案したらしい。
今考えたら、あの張り手は正にゆーこの思惑の一つだったのではないか。そう思えてならない。
そして商店街での出来事の翌日と今日。ちぃは迫真の演技を迫られる。
「ほんと緊張した。それに教室であんな態度を取ることに抵抗があって、ちょっと自己嫌悪に陥ったよ」
昼休みは長すぎると判断し、直ぐに教室を後にしたのだと笑いながら告げる。
「じゃあ、あの日。だいちゃんが屋上に来たのはゆーこが……」
「だろうね。だいちゃんの事も話しちゃったから、ゆーこが差し向けたとしか。ほら、だいちゃんって昼休みは体育館に入りびたりでしょ?」
そうなのだ。私が変な夢を観た日の昼休み、一人になろうと屋上を選んだのもそれが理由だ。来る可能性のある場所を私は選ばない。
そう考えるがお弁当の事を思い出し愕然とする。私はゆーこにこれ以上無い口実を残していったのだ。ゆーこのしたり顔が目に浮かぶ。
「ちょっと待って。じゃあ、校舎裏でのあれも演技だったの?」
「んーん。あれは結構本気だった。初めこそ演技を意識したんだけど、なんだろう。あれは本心だったかな」
私を無視して下校しようとしていたちぃは、初めこそ、そのまま帰ってしまおうと思っていたらしい。しかし、良心の呵責と言うのだろう。無視し続けることに耐えられなくなり、校舎裏へと向かったのだ。
そして私に対しての態度に後悔し、自然と湧いてくる感情に驚くことになる。
演技をする筈が、抑えきれない感情をそのままぶつけてしまったのだ。
ちぃはああいった態度を取ること、そして言い争うような事は苦手なのだと言う。そして意に反しての拒絶反応。だいちゃんを取られたくないという想いが、あの様な態度になってしまったのだろう。
そして私が自分自身の闇を知った今日。
ゆーこはこれ以上、今の状況を続けるのは危険だと判断したらしい。
とりあえず、放課後まで様子を見ながら、これからの事を考えようとしていたが、屋上でだいちゃんを拒絶する私を見て、真っ青になっていたらしい。
「これもごめんなさい。あの時、わたしとゆーこは屋上に居たの。これからの事を話してたんだけどね、だいちゃんとあなたが来たのは予想外だったけど、それ以上にあなたの態度は予想外だった」
絶句するゆーこを見られて、特をしたとちぃは話す。
時間がない。そう感じたゆーこは、放課後直ぐに、私を人気のない廊下へと連れ出したのだ。
「直ぐにわたしの元にね、回復したあなたを向かわせるって言うからさ。待ってたんだけど全然来なくてね。痺れを切らして表まで出て行っちゃたの。ほんと、待つのは苦手かも」
そう苦笑をもらすちぃは、やはり楽しそうだった。
私はと言うと複雑な心境だった。あれだけ辛く、あれだけ涙をこぼしたのだ。正直、正気ではいられない。
しかし一つの疑問が私を支配している。
「どうして? どうしてちぃはそんなに簡単に諦められるの?」
だいちゃんへの気持ちをどうして無視することが出来るのか。
商店街での一件がその証拠だし、校舎裏での一件は演技ではないと言っている。あれだけだいちゃんが他人と共にいるのが嫌だと感じながら、どうしてその気持ちを押さえ込むことが出来る?
「んー。やっぱり、慣れっこになっちゃったから。じゃあ納得しないか」
すこし睨む。先ほども言ったようにそんな事は無理だ。出来たとしても長くは続かないだろう。
「実は……わたしね。何度か告白してるんだ」
え?!
「それこそ、幼い頃のも合わせるともう数え切れないくらいにね。最後に告白したのは中学生のときかな」
「そ、それでどうなったの?」
「ん? ご覧の通り全て玉砕してますが?」
そう言って微笑むちぃ。
なんだかだいちゃんを怨みそうになる。
「それからかな。待とうって決めたの。わたしの気持ちが許すまでね。その間にだいちゃん好みの女になろうとも思ったんだけど駄目だったなぁ」
「どこが駄目なの? ちぃは可愛いし、気が利くし、優しいのに……」
突然その場に立つちぃは、私の手をつかみ立ち上がるよう促す。
そして背伸びをするちぃの背は、私の鼻先までにしか届かない。
「背伸びをしてもわたしの背は届かないね。それが理由かな? だいちゃんが好きになる子ってね、決まってスラっとして背の高い人なの」
俯いてしまう。
こんなにも想い続け、その人の好みに合うよう努力しているのにも関らず、叶わない恋があるという事実に、私は無性に悲しくなってしまう。
世のカップルたちはそういった障害を乗り越えた結果なのだろう。そんな障害すらないカップルも存在するだろうが、それは運命のような物なのではないかと考えてしまう。
「それにもう一つ、理由があるんだよ」
さて、その理由とはなんでしょうか。そう問われるが見当が付かない。
「それはね。あなただから我慢できるの。いや、我慢ってのはおかしいな。なんだか自然に受け入れることが出来るんだよ」
ゆーこと同じことを言う。
私が持っていない物をちぃとゆーこは既に持っている。
そして私が感じている以上に、大切な存在として私が二人の中にいる事に、表現し難い喜びを感じる。
限界だった。
私の目尻からは涙が溢れ、小さい滴が頬を伝って落ちてゆく。
「私は二人ほど出来た人間じゃない。一度捨てようとも思った最低な人間なんだ。ちぃとだいちゃんが付き合えばいい、そう考えてたけど駄目だったの。私は多分、嫉妬してどうしようもなくなっちゃう……」
「それが普通だよ。商店街で見たでしょ? わたしだって嫉妬するし、嫉妬の原因を嫌いになると思う。でも今回は事情が違う。昔から好きなんだもん。わたしのは諦め半分の恋なんだと思うよ」
「それでも……」
「うん、そうだね。諦め半分ってのは嘘かもしれない。でもね、そろそろこの気持ちをどうにかしないといけない、そう思ってたの。振られ続けるのも疲れたしね」
苦笑とも笑みとも言えない表情を私に向けてくる。
「そこにあなたが現れてくれた。確かにだいちゃんへの気持ちはある。けどね、安心っていうのもおかしいかも知れないけど、完全に諦めることが出来るような気がするんだ。だからあなたには諦めて欲しくない。その理由がわたしだって言うのなら、わたしはあなたと一緒には居れなくなっちゃうよ」
目の前にはいるちぃは、どこか儚く、しかしこれでもかって程に私の中に力強く存在している。
どうかな? そんなおどけた様で、それでも真面目に私を見つめている。
健気で人を思い遣れる親友を放したくない。そんな思いからの行動だったのだろう。
私はちぃを抱きしめていた。
「あ、あれ? これって普通逆じゃない?」
涙をそのままにふと笑ってしまう。
「んーん。逆じゃない。私が男だったら、絶対にこうしてる」
ちぃは可愛い。そう連呼し、抱きしめる力を強める。
同情とか、哀れみ、慰めようなんて感情は一切なかった。
ちぃが私に与えてくれる気持ちが、どう仕様も無い程に嬉しくて、喜びだけが私を支配している。
絶対に離さないよう心に誓い。一生親友でいられるように私は願った。
数時間後。
流した涙が完全に乾ききる頃。私たちは談笑していた。
私の右頬には大きな絆創膏が貼り付けてある。存外腫れが酷い様で、ひんやりする絆創膏が心地良い。
そんな私の頬を見て、未練がまだあるのだろう。ちぃがうな垂れる。
「あーぁ。結局想定していたシチュエーションにはならなかったなぁ。それにあの場面は、涙するあなたを慰めようとするわたしが抱きしめてる筈だよ」
くすくすと笑ってしまう。確かに、泣き顔の私がちぃを抱きしめているのは、傍から見たら滑稽だったろう。
「むぅ。やっぱりその左頬わたしに頂戴よ」
「嫌。そんなに簡単には上げないよ」
痛いのはいやだし。
「もう。だいちゃんをあげるんだから、いいじゃない」
それを言われると何も言い返せない。説得された形になっては居るが、後ろめたい気持ちはこれ程までに感じている。
「あ、ごめん。ちょっと冗談が過ぎた」
私の反応が無かったからだろう。焦ったようにちぃが頭を下げる。
「んーん。全然って訳じゃないけど平気」
「……今回は諦めるか。これから何度もそういったチャンスがあるだろうしね」
安堵したのか、スッキリとした面持ちでそう告げるが、私は大いに遠慮したいです。
「それよりほんとに……」
会話の流れがそうさせたのか、私は気づかぬうちにそんな事を口にしていた。
しかし静かに首を横に振るちぃは穏やかな表情をしている。
「もうじゅうぶんでしょ? ってわたしから振ったような感じだけどさ、もうこの話題はやめにしよ?」
静かに頷き、同意を示す。
ちぃに対して後ろめたい気持ちは確かに存在する。しかしその思いすら今のちぃには不要なのだと教えられた、それにだいちゃんに対して失礼なような気がする。
当分は綺麗に無くならない感情かもしれない。それでも私は表に出すことは許されないのだ。
「しかし、ゆーこの考えている事も計り知れないね。収拾が付かなくなって、それっきりになってしまうことは考えなかったのかな? 正直な話、私結構ギリギリだったんだよ」
「それは、その、ごめんなさい」
失言だったか、再度謝られてしまい戸惑ってしまう。
「でもね、ゆーこは兎も角、わたしは大丈夫だと思ったから実行したんだよ」
そう自信満々に告げられると、やはり実感してしまう。
ちぃの強さ、そして私たちを信じて疑わない確かな気持ちを私に示してくる。
やはり今回の事はちぃがいたからこその結果なのだろう。
そう。三角関係なんて上手くゆく例なんかないのだ。
今回はちぃという存在が当事者だった事と、当事者同士の関係が幸いしているが、世に溢れる三角関係なんてそう簡単に円満にはならない。今回の事も円満とは言いがたいのだけど、当事者同士の関係が変わらずにいるのは、やはり良かったと思える。
「私ね、今回の事で二人には色々教えてもらった」
友人と親友の違い。
ただ傍に居られれば良いと言う訳ではない。
ゆーこはライバルにも成り得、信じあえる者が親友だと言う。
確かにそれもあるだろう。しかしちぃの考えや態度から他のことも学んだのだ。
「私ね。ちぃが本当に凄いと思えるところはね。私の為に……、いや、だいちゃんの事も含めて、みんなの為に行動できるところだと思うの。損とか得とか、そう言ったらちょっと違うのかもしれないけど、ちぃは相手のことを想って行動できる。それって凄いことだよ」
今回は私とだいちゃん、双方の為に行動した。
ちぃの立場だったなら、何時でも仲を裂けた筈だ。けれどそうしなかった。
それは、ちぃ自身の気持ちの強さだ。
自身の幸せより、二人を優先した事に感服する。
「いつか私もちぃの様になる。そして親友の為に苦労を厭わない人に、私もなりたい」
自身の幸せも大切だ。しかしそれと同等、あるいはそれ以上に親友の為にこの身を費やしたい。
ちぃを見遣る。
褒めすぎだよと照れているちぃは可愛い。
こんなちぃに相応しい人に私はなりたい。
いや、ならなければならない。胸を張ってちぃの親友なのだと思えるように、私はなるのだ。
「さて、そろそろ帰ってくる頃だよね」
ちぃは時計を確認しそう呟く。
その台詞と同時に頬が熱くなるのを感じる。
そんな私に気づいたちぃは、したり顔で迫ってくる。
「あれぇ? どうしたのかな? そんなに俯いちゃって」
うりうりと頬を突かれる。
これからの事を考えると恥ずかしすぎて死ねる。
「きょ、今日じゃなきゃ駄目?」
「な! 何その上目遣い! 可愛すぎる!」
そう私に抱きつき、ぐりぐりとされるが直ぐに収まり、落ち着いた表情で止めを刺される。
「だめ。これだけは今日じゃなきゃ許さない」
「うー。でも、だいちゃんには酷いことしたし、それに……」
男性への免疫が全く無い私には、それはもう高いハードルにしか思えない。
「それなら尚更早いほうがいいじゃない。多分、だいちゃんかなり傷ついていると思うよ?」
「でも、どうしたら良いのか全然分からないよ……。許してくれるかも分からないし」
「そんなのパンツの一つでも見せてやれば一発だって」
……そうなの?
驚きと疑いの目を向けた所為だろう。ちぃは自信満々に力説する。
「ほら、この前さ、わたしがお弁当を没収された日、覚えてない? わたしが体育館でバスケした日だよ」
「いやあれって、勝利のためっていうか、女の武器を使ったんでしょ?」
「そうそれ! 女の武器! 今回使ってみたら?」
無理!!
確かに許して貰えなさそうであるならば、使っても致し方ないが私には到底出来ない所業だ。
「あぁ、でもやっぱり止めといた方が身の為か」
「そそうだよ。そんなはしたない事したら、逆に嫌われるよ」
……なんですか、その珍獣を見るような目は。
私が戸惑っているとちぃはほんの一瞬、口元を吊り上げた。様に見えたが、満面の笑みで迫り囁いてくる。
「いやいやおまいさん、違いますよ。奴さんはえろえろだと言ってるんです。その身が危ないという意味での『身の為』ですぜ?」
そう低い声で囁くちぃ。顔中が紅潮していくのが分かる。
「あるよぉ。数冊しかなかったけど、奴の部屋には世の男性が使用する物が……」
「……見たことあるの?」
「うむ。隠し場所はプライバシーに反するので教えないけど。あれはすごいよ。なんて言うかな……。とりあえず靴下以外何も付けてなかった」
「え!? それって何か規則があって見せちゃいけない所は隠すんじゃないの?」
「あぁ、隠すべき所にはちゃんと見えないようになってたよ。……どこで買ってんだろうね」
そんなの知らん! って何の話をしているのだろう。興味はあるにはあるのだが今聞くべき話しでは無いような気がする。と言うか聞かなければよかった。
これでは益々だいちゃんの顔を直視できない。
「それじゃあ行っておいで」
そう笑顔で見送ろうとしているが、どこかニヤついているようにも見える。先ほどの会話は意図した物だと気づき、落胆してしまう。
――完全に遊ばれた……。
渋々その場から立ち上がり部屋を出る。
ちぃからしたら激励の言葉なのだろう。
……パンツでも駄目だったら連絡頂戴。わたしがガツンと言ってやるから!
そう笑顔で送り出された。
絶対に使わないと決意し、私は携帯を取り出す。
決戦は近所の公園に指定。その場所にだいちゃんを呼び出すことにする。
現状ですら男性の部屋に入る勇気が無いのに、ちぃとのあの会話の所為で当分は近寄れない。脳裏をかすめた瞬間におかしくなってしまいそうだ。
気持ちを落ち着かせるために、ゆっくりとした歩幅で公園へと向かう。
途中、ちぃの想いとゆーこの想い、それらが私の中に在るのを確認する。
暖かく、ほんの少し騒がしいこの気持ちがあれば、私が私で居られるような気がする。
直ぐそこに感じられる安堵感。二度と手を離さないと誓い、私が二人にとってこんな存在に成れるよう願う。
あの暗闇を忘れる訳にはいかない。
私を引っ叩いてまで連れ戻してくれる者がいる。しかし、その手にばかり頼っている訳にもいかない。逆に私が引っ張って上げれる力を私は必要としているのだ。
先でも後でもない。隣に並び歩きたい。
お互いを信用しあえる者。
お互いを認め合い、任せられる者。
苦労を厭わず、手を差し伸べあえる者。
それを親友と呼ぶのかどうか分からない。だけど、友人というのも違う気がする。
だから私は、名称のない、枠組みされていない場所に収めた。
私は幸せ者かも知れない。
一生の内に出逢えるか分からない者が、二人も居るのだから。
二人の大切さを再認識し、今日という日を思い出す。
真っ暗闇から一変し、眩しく、暖かい世界に連れ戻された。その衝撃と感謝の想いと言ったら、表現できないくらいだ。
そして思い遣る気持ち。
他人の幸せを自身の幸せの様に扱える事。それこそ、親が子に向ける愛情のような物が、私に向けられていた事実。
少し言い過ぎなのかも知れないが、私自身感じてしまったものだ。否定はされても、私の気持ちは変わらないだろう。
今日だけで色々ありすぎた。
そして私の中にあるモノも、劇的に変化しようとしている。そんな気がする。
この気持ちを忘れずにいよう。そう誓いながら歩き進むが、これからまだ続くのだと思うと、心地の良い疲労感を感じるのだった。