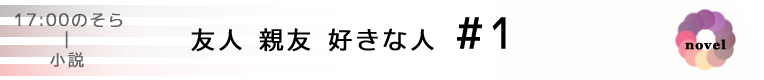快晴を喜んでいるように、新緑が木漏れ日を躍らせている。
春とも夏とも言えない季節、いや春なのだけど、最近は特に暖かく桜が散ってしまったそんな季節。
窓際に座り、黒板に書かれた記号式がなんだか睡魔を呼び寄せている。
しかし、そんな睡魔には目も繰れず、外を眺め必死に押さえ込もうと奮闘中。
腹の虫。
十二時はとっくに過ぎ去り、後数分の我慢なのだが、そろそろ押さえられないくらいにお腹が騒ぎ出している。
辺りに気を配ると静寂とは言えないがとても静かだ。普段と変わらない授業風景なのだけど、こういった時は余計に静かに感じてしまう。自分に都合の悪い方に感じてしまうのは、何かの心理が働いているのだろうが、それにしても静か過ぎる。
こんな状況で腹の音はちょこっとと言わずかなり恥ずかしい。
吐息混じりに頑張れ自分! と励ましている時である。教室中に響き渡る程の音量でそれはもう遠慮なしに腹の音が鳴った。
きゅるるといった可愛らしい? 音が響き渡り、全員が一斉に振り向く。
その視線の中心には小柄な女生徒が一人。当たり前だが同級生でクラスメイトの愛称『ちぃ』が黒板を真面目な顔で睨みつけていた。
辺りを見渡し、あれ?聞こえちゃった? といった表情を作り、すっくと立ち上がる。
「先生! クラスを代表してあたしのお腹が悲鳴を上げています! 早弁オッケー条約にサインをください」
クラスの全員が救いと呆れを含んだ表情で教壇に立つ先生を注視する。
「早弁は勝手にしろ。だが、それは休み時間限定の話だ」
「では、こっそり早弁オッケー条約は――」
「見つけたら俺がその弁当を食ってやる。それでもいいならサインをしよう」
静寂が訪れる、ちぃはノートにマジックペンで文字を書き、勝ち誇った表情でそれを掲げる。
勝訴! そう書かれた文字はバランスも良く、綺麗な字なのだ。
辺りからは歓声と拍手が厳かに送られている。
「お前らぁ、後数分なんだから我慢しろよ」
そう言って授業を再開する先生を横目に、席に着いたちぃは教科書とノートで障壁を築いている。
あれで隠しているつもりなのだろう、早速お弁当を広げ両手を合わせている。
「では、戴きます」
誰もが冷や汗ものの台詞を自然と鼓膜がキャッチする。
その台詞は例外無く教師にも聞こえているわけで、ちぃが一口目を口にしたのを確認し歩み寄る。
ご愁傷様。ちぃ!前、前! そんな囁きにすら気が付かないちぃ。とっても哀れである。
「先生は言いました。このクラスの者達が証人です。と言うことで……」
教師がちぃのお弁当を取り上げる。あぁん、そんな悲壮な声を上げ、呆気に取られている。
「何故ばれた!」
一同が再確認する時である。今日も平和で何時も通りなのだと。こいつのお陰で世の中は巧く回っていると、そう実感する時だった。現に最後尾に陣取っている早弁組みは、昼休みを有意義に過ごすために、今まさにこの時、教科書一枚の障壁にも関らず難なくお弁当を空にしている。
「あとで、空の弁当箱渡すから職員室に取りに来いよ」
平然と授業に戻る教師。愕然とうな垂れるちぃ。いつもの光景が時間を忘れさせ、気が付いたら終了のチャイムまであと僅かだった。
木漏れ日が踊っている。
今日は教室ではなく、どこか日の当たる所でご飯にしよう。
そう思うと待ち遠しくて仕方が無かった。
昼休み。
外は快晴で暖かい日差しが私を誘っている気がしていた。
この陽気の中を友達とお弁当を食べるなんて、それはもう素敵で楽しい過ごし方なのではないか。
そう、絶対にこっちの方がいいのに、どうして私は体育館なんかで食事を取っているのだろう。
数名の男子がバスケを楽しんでいる。
彼らは練習熱心なバスケ部員というわけではなく、昼休みを机に向って過ごす事が出来ないってだけなのだろう。
そんな男子達に混ざって一緒に身体を動かしている女子が一人。
「うおっしゃぁ! どんなもんだ!」
小柄な女子がシュートを決めガッツポーズ。こちらを指し興奮気味に声を上げる。
「見た? わたしの華麗なシュート!」
えぇえぇ、それもうバッチリ目撃させてもらいましたよ。可愛らしいライオンがプリントされたパンツを。
「くそ! 気が散る!」「バカが、あんなのに惑わされるお前が悪いんだよ」「そういうお前だって、ガン見してプレイがお粗末じゃん」
男子達は焦っているようで、それでいて今の状況を楽しんでいるみたいだった。
ちなみに、このゲームの敗者は勝者に好きな物を奢るという、ちょっとした賭けが同意の下で組まれている。
「ちぃ! そろそろジャージを履け! これ以上の点差はハンデにならん!」
「え〜、もう飽きちゃったかこのパンツ。ん〜、そうだな。履くか?」
そうしろと言う男子が大半かと思いきや、逆だった。「俺は飽きてない! と言うか一回しか見てないぞ!」「飽きたとは違うんだけど新鮮さがなぁ」「俺まだ見てねぇ!」と言うように馬鹿ばっかだった。
「ちぃー! おいで! 少しは恥じらいを知りなさい!」
そう私が声を上げる。周りからブーイングの砂塵が巻き起こるが小さいので気にしない。
休憩といいながらこちらへと歩み寄るちぃは、機嫌が良い様で満面の笑みを湛えている。
「もう。あんたも少しは恥らいなさいよ」
「ん〜、分かってんだけどね。なんでだろう、恥ずかしさが微塵も湧いてこないんだよ」
「それってもしかして、勝つ為とか?」
「そうなのかも。どうしても勝たなければならないからね。聞こえない? お腹の音」
両手を腰に据え、胸を張るちぃ。
微かに聞こえる腹の音はもう限界だと悲鳴を上げていた。
午前最後の授業でちぃの昼食は没収され、それは既に教師の胃袋へと納まっているのだろう。自業自得と言えなくもないが、公言通りに空にしなくてもいい様な気がする。情けを知らない、または冗談を知らない教師ってのも珍しい存在だ。
しかし、だからと言ってあの馬鹿共に無償で拝ませるなんて。
サービス精神というのだろうか、「当ててんのよ」的な意味合いかな。
――そんな訳ねぇ。
まぁ、パンチラも一つの作戦。ここで勝って置けばコッペパンとパックジュースくらいは手に入るだろう。
「うっしゃあ、コロッケパン! 待ってろよぉ!」
それはもう時間帯的に無理な話だとは突っ込まないで置いた。ほぼ毎日が弁当組みのちぃには購買部での戦争を知らない。この事を知ってしまうと本気で落ち込んで勝てる勝負にも負けてしまいそうだ。
スカートの下にジャージを装着したちぃを見送り、一息。ゲームが再開される。
私は食べかけの弁当に取り掛かった。
二十点差。制限時間はあと十分ちょい、なんとか逃げ切れるだろう。地質五対四のバスケは白熱し始めている。
黙々とお弁当に箸を伸ばしているときだ。こちら側とは逆の方にあるコートで歓声が上がる。
興味はなかったが視線が自然とそちらに向いてしまう私は、野次馬スキルが備わっているのかもしれない。
そのコートでは観戦者が大勢取り巻いており、コートでプレイしている生徒は良く見えない。
「あれ? 一人なのか」
たこさんウインナーを口にした時だ、声を掛けきた愛称『だいちゃん』はクラスは違えど、男子の中では一番仲が良い。
高校生活が始まってまだ一ヶ月にも満たないのに、仲の良い男子がいるというのは私からしたら奇跡に近い。中学から一緒の男子も居るのだが、だいちゃんほど仲がいい訳ではない。では、何故友達と呼べるかと言うと、ちぃの存在が大きいからだろう。
ちぃとだいちゃんは幼馴染だ。ちぃとはこの高校で初めて出会った親友なのだが、その親友にもれなく付いてきたのがだいちゃんである。
「ん。そだよ?」
「へぇ、珍しい。長女は? 今日は別なのか?」
ほれ、あそこ。
たこさんを咀嚼しながらあごでしゃくる。
長女こと愛称『ゆーこ』は、別のコートで男子の応援に夢中だ。
ここでゆーこが長女と呼ばれる由縁を話して置かなくてはならないだろうか。
別にゆーこの家族構成がそう呼ばせているわけではない。現にゆーこには姉が居る。
では、何故? となる訳だが。ゆーこ、私、ちぃは始業式当日にちょっとしたハプニングに見舞われて、それが切っ掛けで仲良くなったのだけど、それからだ。
『北高三姉妹』 その通称と共に、長女のゆーこ、次女の私、三女のちぃと呼ばれるようになる。
それが一年生の間だけなら良かったのだが、最近では上級生達にもそう呼ばれる事がある。
と、控えめに言っては見たが『北高三姉妹』という通称で分かるように、校外にもその名が知れ渡ってしまっている。
こっちとしては、はた迷惑なのだがあの出来事が無かったら、ちぃたちとここまで仲良くならずに居たのかも知れない。そう思うと不満はあれ、仕方がないかと考えてしまう。
「ねぇ、あそこ。あそこで何やってんの?」
「あぁ、あれはほら、知らないか? 女子バスに入部した一年の話」
曖昧に頷きながらも何のことだかさっぱりだ。
「今年入った一年が居るんだけど、その中でダントツに巧い奴が二人居るんだよ。既に上級生を凌ぐほどの実力があるらしくてな、期待のエースなんて言われてる。なんて言ったか忘れたが通称まであるらしいぞ」
かわいそうに。私の場合はそっとして置いて欲しいタイプなので、北高三姉妹なんて呼ばれるのは死ぬほど恥ずかしい。
しかしどうなのだろう。スポーツマンは目立ちたがりな印象があるから、別に苦には思わないのだろうか。
「その二人が今プレイしてる訳だよ。俺も少し見てきたけど、うん、凄い動きするわあいつ等」
さいですか。
「お前、興味ないだろ」
「え? いやぁ、まさか。無い事はないけど……」
「はしゃぐ程興味はないと」
まあ、そうね。
なにやらニヤニヤと小バカにした視線を感じ、私はこちらのゲームに視線を戻し、話題を逸らす。
「だいちゃん、飯は?」
「もう食ったよ。腹ごなしに来たんだけど、なんかスゲー真剣だからさ。なかなか入れん」
たしかに、ちぃたちのゲームは既に点差がなくなりつつある。
明らかにちぃの存在がチーム全体の動きを空回りさせている。
毎日のように組んでいるチームではないにしろ、それなりのプレイヤーが揃っている中では、やはり力不足は否めない。体調が万全のちぃであるならば、それなりに活躍できたであろうに。勿体無いかなコッペパン。
「あ、今日数Iで宿題出るよ。三時間目の授業で出された」
「マジで! くそぉ。今日はゲーム三昧だと思ったのに……。ってなんで知ってんの?これから数Iあるってこと」
あ、しくりやがりましたこの私。
最近はちぃの心境も変化し始めて五月蝿いったらないのだが、これだけは当事者の問題なので口には出せない。
そう、ちぃ本人には自覚が無いようなのだが、目に見えてだいちゃんの話題が多い。
幼馴染という名の垣根を跨ぎ始めた事にすら気が付かずにいるちぃは、それはもう可愛いったらない。気付けば『だいちゃん』という台詞を口にしている。しかもその台詞を言う時の目が乙女なのだ。
なのでちぃの知りうるだいちゃん情報は既に筒抜けだ。
「そりゃあ、だいちゃんのクラスにも友達が居るからだよ。その子から聞いたの」
「なるほど」
――嘘だけどね。私、自分で言うのもなんだけど、友達少ないんだ。はは……。
しかしだいちゃんもそれ程気にしていないようで、追求はしてこない。
「じゃあ今日は一緒にやらね?」
「いいねぇ。ちぃの家でいい?」
「あ、いや、その……」
? なに? その間は。
何かを逡巡するように辺りを見渡し、落ち着かないだいちゃん。
そして考えが纏まったのだろう、こちらを見つめ何かを口にしかけた時、ホイッスルが体育館全体に鳴り響く。
目の前で繰り広げられていたゲームが終了したのだ。てかどっから持って来たそのホイッスル。
ホイッスル後の野太い歓喜がちぃの敗北を決定付けていた。
うな垂れ、千鳥足でこちらに向うちぃは半ベソ状態。とても見ていられない無残な姿だ。
「負けた。あたしのコロッケパンが……」
「大丈夫? お弁当、半分だけど食べる?」
「いいの?」
頷く私に泣きながら抱きつくちぃは、とても温かい。と言うか暑苦しい。
どぉどう。そう言ってなだめながらお弁当を差し出すと、飛びつくようにお弁当を受け取り空にしていく。
あははは、餌付けしてるみたいで面白い。
「そう言えばだいちゃん。さっき何か言いかけなかった?」
「いや、なんでもない」
そう? なんでもないっていう顔してないけど、本人が言うのだからそうなのだろう。
「ん? なんの話?」
「今日三人で宿題しようって話。ちぃの家は今日大丈夫?」
「もちろん! 大丈夫じゃない日は無い位、大丈夫だよ」
言いたい事は分かるが何を言っているのだろう台詞に、私は堪らずちぃの頭を撫でる。
「それじゃあ、また後でな」
そう言って、コートの中へ入っていくだいちゃん。チームを入れ替えて一戦交えるみたいだ。
そしてちぃの眼差しはだいちゃんに注がれており、お弁当を突く箸捌きは疎かになっている。
――全くもってかわいいなぁ。
体育館に差し込む温かい日差しは、この空間を明るく照らしている。
外での昼食は残念とも思っていたのだが、実際場所なんて関係ないのかもしれない。一番重要なのは傍に誰がいるかという事だ。
こんな昼食も悪くない。そう感じる昼下がりなのだった。
◆ ◆ ◆
町を彩る紅い光が帰路に着いた三人を照らしている。
「おなかへったぁ。どこかに寄ろうよ」
「買い食い厳禁。入学して一ヶ月も経たないうちに破るなんて出来ないよ」
「んもぉ、真面目なんだから! だいちゃんも説得してよ」
「ん〜、俺は別に腹減ってないからいいよ」
「えぇー」
当たり障りの無い会話。
影を長くハッキリと落とすこの時間を三者三様に歩き、そしてまた物思いに忙しい。
一人は、何時までもこの時間が続けば良いと願い、しかしそんな事は不可能だと理解している者。
一人は、楽しい時間を過ごしたいと願い、しかし最近変わり始めている自身の事で精一杯な者。
一人は、経験したことの無い感情を持て余し、どのようにして伝えたものかと悩み苦しむ者。
性別の違いを理解し、出会った二人。
家族のような鬱陶しさと暖かさを共に感じている昔馴染み。
当たり前の感情。
当たり前の言葉。
繰り返される感慨。
さして変化の無いこの世界。
されど様々な事が起こりうるこの世界を三人は当たり前のように歩いている。
鼻をくんくんと動かし、この商店街を包む様々な香りを追いかけているちぃは見ていて飽きない。
「やきとり! 時代はやきとりだよ!」
そう言って私の袖をクイクイと引っ張って行こうとするのをやんわりとあしらい、ちぃの隣を無言で歩くだいちゃんの方へと視線を向ける。
ちょっぴり険しい顔をして悩んでいる様子だ。
何時も以上に無口なだいちゃんを見るのは初めてのことで、なんだか心配になってくる。
こんな時、素直に役に立てないだろうかと思うが、私では役には立てないのだろう。
異性には相談し難い話題かも知れないし、その懸案によっては異性間の考え方の違いもある。
それに私自身、まだ男性という者の扱い方を良く知らない。
小、中学と共学であったが、男子にはあまり良い印象は無く、関らないようにしていたし、その所為かなんだか気恥ずかしい。
だいちゃんとは大分話せるようになってるけど、それだけだし理解しているとは言い難い。
こんな私でも何時かは彼氏なんかを作って過ごしているのかな、なんて考えることもあるが、やはり明確な想像は出来ず、居ないのが当たり前じゃない? とも思ってしまう。それはそれで有りかな、なんて考えてしまう始末だし。
当分は夢見る少女とは言わないまでも、まだまだ遠い幻想のお話だ。
気づかぬ内に恋愛方面へと思考が向いてしまうのも、私の中での恋愛は憧れの部類に入っているのだろう。
そんな考え事が覚めるや否や、顔が焼けるように熱い。
気づけば目の前で、笑顔のおっちゃんがやきとりを焼いていた。
「嬢ちゃん、一本一得か?!」
笑顔でお断りし、隣を振り向けばちぃが焼き立てを強請って交渉中。後ろへと振り向けば夕日を睨み付けているだいちゃんが黄昏中。
なんだこれ。
あべこべで一体感が全く無い。それでいて、落ち着くこの光景。
それぞれが好き勝手に行動し、それでいて、気にかけているこの関係。
頬が勝手に緩むのを感じ、自然に微笑んでしまうのを自覚する。
「ん? どしたの? なんかニヤニヤしてるよ?」
私の顔を覗き込み、この笑顔が移ったのだろうか。ちぃも微笑をたたえている。
「ん。どうもしてないよ。それより見て、だいちゃんが格好つけてたそがれてる」
ニヤニヤが止まらないあごでしゃくる。ちぃは導かれるように首を傾げ、だいちゃんへと目を向けた。
「あっ」
そして、一切動けなくなってしまうちぃ。
想像通りというかなんと言うか、見とれてしまいましたよこの娘。
たぶん、ちぃの瞳には、この情景にキラッキラなエフェクトが掛かって見えているのだろう。私には逆に心配になるくらい悩んでいる様子にしか見えない。
これが恋の力なのか。
未だ未知数のその力に興味が俄然湧いてくるし、私も経験してみたいと思うのだが、こればっかりはタイミングのような気がしてならない。
遠い昔の物語でもあるように、タイミングの悪い恋は実った試しがない。
どんなに愛し合っていても、時代や環境、世界がそれを黙って見ていない。引き剥がされ、災難と絶望を味わう。
そうなのだ。何事もタイミングこれ大事。
呆けている二人をこのままにしておく訳にもいかず、私がスイッチ役にならねばならない。
一人は惚けているので放っておいても自然と覚ますだろうが、もう一人は深刻だ。
その悩める問題をどうにかしなければ、帰ってこれないのだから。
ここいらで友人の一人である私が一肌脱ごうではないか!
なんて意気込んではみるものの、やはりどのように接するべきなのか全く検討も付かないので、とりあえず軽い感じでやってみようと決意する。
先ほどまでの表情にちょっぴりニヤニヤ度を増しながら、だいちゃんへと接近していく。
「どしたの? なんか物凄くたそがれてるけど、なにかあった?」
完璧だ。この気軽に話してみなよオーラがなんとも良い感じではないだろうか。別に話してくれなくても良いし、話してくれたら相談に乗るよといったニュアンス漂う台詞も絶妙で素敵だ。
それに止めのこの表情。ちょっとおどけた感じがまた相手に威圧感を与えないベストな選択。
私は心の中でガッツポーズを決めだいちゃんを見遣るが、そのだいちゃんはノーリアクション。
完璧だと思われたこの作戦は、宙へ舞い散ってしまったらしい。
ショックの余り、だいちゃんの顔をまじまじと見詰めてしまう。
そこで気づかされたのが、存外、だいちゃんは背が高いことに気が付いた。
気にしたことが無かった所為もあるだろうが、この発見は後に大きな反響を巻き起こすかもしれない。
なんせ私自身、背が高い方で女子の平均を余裕でクリアーしている。それでも男子平均には程遠いいのだけど、やはりちょっとしたコンプレックスなのは変わりない。
だからこそ、背の高い男子の隣に並ぶと落ち着いてしまうのだ。これで女子扱いされるのではないかと。
それに幼少の頃にそれが原因で大いにからかわれた事があるものだから、やはり背の高い男子の隣が一番落ち着く。
ついでなのでもっと観察をしようと背を伸ばす。
うん。以外に整った男らしい顔をしている。密かに一部の女子達に人気なのが納得できる。
そしてなんと! 驚くことに睫毛が長い! なんとまぁ羨ましい限りだ! まぁ、長いだけなのだけど。
お? 髭の剃り残しがある。まぁ、まだ剃り慣れていないのだろうけど、ここは鬼教官の私としては減点! いや、私は全く気にしないけど、あの一部の女子達が見たら呆れてしまうかなぁっていう、心配心からの減点だよ。身だしなみ、これ大切。
あ、綺麗な瞳をしてますね。ハッキリとした白目と黒目が高評価です。……ん? 瞳?
気づけば視線がバッチリと絡み合っていた。
驚きの勢いと共に大きく仰け反る。
「ちょ、ちょっと! びっくりさせないでよ!」
「……で? なにが高評価だって?」
うがつ! 声に出ていたみたいだ。
「ん、まぁ、隠してもしょうがないから言うけど、瞳が綺麗だなぁって。だいちゃんて以外に素敵顔だね」
そう笑顔で言ってみるが、動揺を隠しているのがバレバレなのだろう。だいちゃんがニヤニヤと接近してくる。
「へぇ、俺って素敵顔なのか。初めて言われたよ。自信付いちゃうな」
「自信? やっぱり悩み事があるんだ」
話を本来のと言うべきか、私が求めていた話題へと振る。
「最近、口数少ないし。なんだか呆けてる事が多いような気がしてたから、なにか悩み事でもあるのかなって」
「そりゃあ、悩み事の一つや二つあって当然だろ? 人間だもの」
唐突のパロディーを持ち出され、ふっと笑いあってしまう。
なんだか軽く流されたように思うが、やはり私には相談できない事で悩んでいるのだ。こうなればもう私に出来ることは何も無い。
「俺の事なんかよりあいつをどうにかした方が良いんじゃないか?」
そう示される方へ向き直ると、ちぃは未だこちらに戻っていない様子だった。
右手に持ったやきとりのタレが包装紙を伝い右手を大いに汚している。
「ちぃ? 大丈夫?」
いや、明らかに問題ありなのにこの台詞はミスマッチだ。
しかし、そんな問いかけにも返事を寄越さないちぃは重度の恋の病なのだろう。
とりあえずやきとりをもう一度包装してもらい、ハンカチでちぃの右手を拭いていく。
「べたべたになってるけど、とりあえずの応急処置。この辺水ないしね」
そう甲斐甲斐しく、てきぱきと拭いている時だ。
「……わたし、駄目だ」
不意に漏れ聞こえるちぃの声。今までに一度も聞いたことの無い声色でそう呟いた。
悲しみ・哀れみ・拒絶に怒り。それらネガティブなものを全て含んだ声。
驚き、ちぃの顔を見遣る。
ちぃ自身も驚きが大半を占めるその表情には、どこか哀しみも混じっている。
「どうしたの? ちぃ……」
そう手を伸ばした時だ。今にも泣き出しそうな苦笑いが私を見詰める。
「ぃやだ……。――嫌だ!!」
突然駆け出し、瞬く間に遠くへと行ってしまう。
何が起こったのか理解できず、私はその場に立ち竦んでしまう。
先ほどまでの雰囲気から一変し、辺りを包む空気が一瞬にして判らなくなる。何時も通りだった筈の帰り道が、薄暗く、全く知らない物に変わってしまい背筋が泡立つ。
嫌な予感。
得体の知れない感情が私を包み始めているのではないかという、不安な気持ち。
「だいちゃん、ちぃが……」
助けを請うような表情になっていたのだろう。
「俺にも判らん。……ごめん。今日は俺も一人で帰るわ」
哀れみを含んだ、遣る瀬無い表情で私を一瞥し、歩き去ってしまう。
……なんだこれ。
商店街の喧騒が遠くに聞こえる。
先ほどまでは私もその一部だった筈なのに、今では遠く、隔離されてしまったかのように感じる。
どうすればいいのか検討も付かず、私はただ彷徨うことしか出来なかった。
「うん。そうだね、それじゃあ、また明日学校で」
そう告げて携帯電話を閉じる。
ゆーことの会話で幾らか気晴らしが出来たものの、やはりそう簡単に全てが晴れることは無かった。
相談してみようとも思ったのだが、如何せん、状況も把握しきれていない状態なので、どのように話してよいのか分からず、また話すべきなのかも判断が付かなかったものだから、結局は何時もの他愛ないおしゃべりで終わってしまった。
今日の出来事が思い起こされる。
ちぃの言葉、表情がどうしようもなく脳裏をかすめ居たたまれなくなる。
原因はやはり、だいちゃんなのだろう。
いや、間接的に関係があるってだけで、直接的な原因は私にあるのかもしれない。
あの時の私は何時もよりも積極的だったように思う。いくら親しくなってきたとはいえ、あれだけ異性に接近したことは今までに無かったことだ。そう考えると赤面物なのだけど。
その行動によってのちぃの変化だとするのならばやはり。
――嫉妬、かな?
今までのちぃならばそんな筈はと思ってしまうが、あの反応を見ると否定できない。
ちぃの中で大きく、そして確立しつつある感情を想像すると、答えは一つしかないように思われた。
これからは慎重に行動しなければならないだろう、なんだか取り返しの付かないことになりそうで怖い。
それに二度とあのようなちぃは見たくない。
「はぁ……」
溜息と共に時計に目を遣ると、既に十時を回っている。
集まって片付ける筈だった宿題は手付かずのままだし、このまま呆けていたら、答えの出ない問答を続けてしまいそうだ。
重たい気分を無理やり持ち上げ、机へと向かう。
鞄から教科書類を机に広げ一呼吸し、気合を入れたところで、もう一つの懸案が思い起こされた。
私が抱く可能性のある感情。
決してあってはならない気持ち。
そう、絶対に好きになってはならない。
ちぃは親友で、だいちゃんは友人だ。
親友と友人。どちらを優先するなんて、そんなこと考えたくは無い。
しかしそれが変わってしまい、だいちゃんが好きな人になってしまったら、その時の私はどうするのだろう。
親友と好きな人を天秤に掛けることなんて出来るのだろうか。
――いやな考え方。
大切なものに優劣なんて関係ないというのに。
よくある質問に、仕事と恋人、どちらが大切かなんてものがあるけど、そんなものただの意地悪な質問にしか思えない。
両方大切なものなのに、どちらかを選べなんて私には出来ない。
そうだ、好きにならなければそんな選択に迫られない。
私は決して好きになってはいけないのだ。それに、ちぃとだいちゃんはとってもお似合いのような気がする。
あの二人が楽しそうにしていると、なんだか私も楽しくなってしまうし、やはり二人には笑っていてほしい。
どうしてあの二人は付き合っていないのだろうと、初めこそ思っていたのだが、ちぃを知るうちに得心した。
だから今の状況は正にチャンスなのでは無いだろうか。
今日の出来事でちぃは自身の気持ちに気づいただろう。確証はないがそんな気がする。
そう結論付けると私のするべき事はそう多くは無い。
放って置いてもくっつくような気がするが、早く二人の笑顔が見たい。
二人の合意がなせるチャンスを邪魔しないよう見守りながら、こちらからチャンスを作ってあげれば良いだけだ。
家も近いのだし、既にくっついているといいのだけど。
何はともあれ、全ては明日だ。
ちゃっちゃと宿題を終わらせ、今日は早くに寝よう。
そう思い宿題に取り掛かるが、苦手な数学という事で、結局日付が変わる頃に就寝した。
◆ ◆ ◆
翌朝。
これまで味わったことの無い幸福感と共に目が覚める。
良い夢を見たのだ。そう、決して悪くない夢。何時までも続いて欲しいと素直に思えるそんな夢だ。
しかし、頭が活性化していくにつれ、自己嫌悪と共に気落ちしてゆく。
どうしてこんな夢を見た。告白される夢なんて。
そう疑問に思うが、それはすぐに解決される。
昨日のあの出来事。それと昨夜、ベッドに横になってからも散々二人の事を考えた所為なのだろうけど、なんて間の悪い夢なのだろう。もう少しマシな夢は無かったのだろうか。
それに未だに残るこの幸福感がさらに私を追い詰める。
あれだけ好きになってはいけないと言い聞かせたのに、既に手遅れのような気がする。
――違う。……違う!
こんな物ただのまやかしだ。現実じゃない、幻想で妄想なのだ。
深く考えてはいけない。そう思いベッドから立ち上がり洗面所へと向かう時だ。
ふと気づいた事が一つある。
だいちゃんの気持ち。
ちぃが好きなのだから、当然のようにだいちゃんもちぃの事を想っているのだと決め付けていた。しかしそうだったのなら、だいちゃんの性格上、もっと早くに二人は進展していてもおかしくないように思える。
だいちゃん自身、ちぃがその気持ちに気づくまで待っている。その可能性も無くはないが、違うような気がする。
待つことは苦手だろうし、相手から言ってくるのを待つような性格じゃない。と思う。
それか、やはり幼馴染というカテゴリが邪魔をしているのかもしれない。
それだけだったらどんなに良いだろうと考えるが、最悪の考えもまた湧いてくる。
別に好きな人が居るかも知れないという可能性だ。この可能性は否定したい。どう足掻こうがちぃは辛い状況になってしまうからだ。
しかし確かめようにも術が無い。
だいちゃんを悩ませている問題。それが無性に気になってどうしようもなくなる。
こうなると居ても経っても居られない。
私は制服に着替え、朝食もそこそこに足早に家を出た。
何時もの通学路。
朝の商店街には、夕時とは違った喧騒がある。
スーツ姿のサラリーマンや様々な制服を着た学生たちで賑わっているのだが、商店などには目もくれず、駅を目指して歩を進めている。
駅を過ぎた辺りになると、私と同じ制服を着た学生が目立つようになり、他の者は駅の改札へと吸い込まれるように構内へと消えてゆく。
そして何時もの待ち合わせ場所。
ゆーこ、ちぃ、偶にだいちゃんとでここに落ち合って学校へ行くのだが、今日はまだ誰の姿も無い。
特にそういった約束をしている訳ではないが、高校生活初日から自然と集まるようになったのだ。
――ちょっと早すぎたかな。
時計を見ると、普段より二十分程早く到着してしまっている。
先に行くという選択肢は微塵も無く、朝の空気を吸いながら待つことにした。
やはり何もしていないと考えてしまうな。
昨日ちぃが走り去った現場がここから伺うことが出来た。
蘇える光景。突然の出来事に立ち尽くすことしか出来なかった自分を思うと、なんだか腹が立ってくる。
それにだいちゃんの態度もそうだ。自分のことで精一杯なのだろうけど、もう少し気を使ってくれても良いような気がする。
ちぃの事では私よりだいちゃんの方が詳しいだろうに。
だからこそのあの態度だったのか。それとも他に理由があったのか。
「だいちゃんには聞きたいことが山盛りだ」
そう呟き、気合を入れ直そうにも、今朝の夢が脳裏をかすめ、逆にしぼんでしまう。
言いようの無い幸福感。もう一度と想い求めてしまう感情。
この感情と共に湧き上がる恐怖心と同時に、だいちゃんに会ってはならないという予感が芽生える。
今日は駄目だ。夢の残り香が私を包んでいる間は会ってはいけない。一日経てば綺麗さっぱり忘れられるような気がする。
それにちぃとも会いたくない。
昨日までは能天気な、周囲の雰囲気を読むのが苦手なのだと思っていたが、果たしてそうだったろうか。
たった半月足らずで、人一人を知ることなんて出来やしない。
それに私たちが知り合うきっかけになったのも、ちぃが私とゆーこ、それぞれの気持ちを汲んでくれていたからこそ、ここまで仲良くなれたのではないのか。
こんな調子では会えないと確信めいた結論に達する。ちぃには私のこの感情を読まれる訳には行かない。
時間は先ほどから十分程度しか進んでいない。引き返すのならば今だと思い、踵を返すその先にはゆーこが居た。視線がバッチリ合ってしまう。
「おはよう。今日は早いんだね」
はぁ、この癒し系で和み度全開の笑顔を見ると嘘を突き通す自信が湧かない。
「おはよう。なんだか急に具合が悪くなったから、今日は早退するね」
苦笑いを懸命に作り、どうにかこの場から立ち去ろうとするが、ゆーこはそんなに甘くは無かった。
「早退? まだ登校すらしてないじゃない」
そう、通常の思考とはほんの少しだけ外れてしまっているゆーこの台詞。そっちじゃないだろ? 私自身、早退はどうかと思うけど。
「うん、そうなんだけど、この体調がこれから悪化しますよって私に語りかけて来るんだよ」
「? 顔色とか普通だと思うけど……。……今日なの?」
「いや、まだ先だけど……」
うがつ! つい素直に反応してしまったじゃないか! そうしておけば、素直に帰らせてもらえたかも知れないのに、なんたる失態。
「とりあえず、保健室行こうか?」
いやいやゆーこさん。ここからなら学校より家のほうが近いです。
そんな押し問答が三十分近くも繰り広げたものだから、結局時間ぎりぎりに登校する羽目になった。
その途中、ちぃが何時もの場所に顔を出さなかったことに、少なからず安堵はしていたが、同じクラスなので結局顔を合わせる事になるのだと、昇降口に到着した時に気が付いた。
予鈴のチャイムと共に教室へ到着し、足早に自分の席に着く。
ちぃの席を確認したが本人はおらず、空席だった。
なにかあったのだろうか。そう心配もするが今は会わずに済むという安堵のほうが大きかった。
ちぃは三時間目の途中で登校してきた。
こっそりと様子を伺うと体調が優れないのだろうか、俯き加減で授業を受けている。
休み時間になるや机に突っ伏し、心配する女生徒に声を掛けられるが生返事しか寄こさない。
そして昼休みと同時に席を立つちぃは、そのまま教室を後にする。
普段が普段なだけに、クラス一同はちぃの話題で持ちきりだ。
私も何度か声を掛けようか迷ったのだが、躊躇うことしか出来なくて結局は声を掛けられずに居る。
「ちぃ。どうしんだろう、調子悪いみたいなんだけど何か知ってる?」
ゆーこがお弁当を片手にそう聞いてくる。
原因であろう昨日の出来事を話すべきか迷ったのだが、今は自分の事で精一杯で曖昧な返事になってしまう。
私自身一刻も早くこの場から立ち去りたい気分だった。
だいちゃんは別のクラスだから今のところ顔を見なくて済んでいる。しかしこのクラスに顔を出さない保障はどこにも無い。
「ごめん、ゆーこ。私もちょっと席外すね」
「え。ご飯は?」
家に帰ってから食べる。
後から考えればこれほど理解しがたい台詞もないだろう。そう言い残し、教室を後にする。
目指すは屋上。利用したことは数えるくらいにしかないが、人気はないのだろう。その全てが無人という、なんとも好都合な場所で、一人になりたい時の定番となる名所だ。
簡素なドアノブに手を掛け扉を押し開ける。何故だか分からないが、どんな扉よりも重たく感じた。
吹き込む風。眩しい陽光。こんな気分でなかったらどんなに清々しい光景だろう。
しかし、今の私にはそんなことに感けている余裕は無く、落ち着けそうな場所を探し歩く。
柵に囲まれた空調機器などを横目に、立ち入り禁止と張り紙された機器室、塔屋へと歩み寄る。
周囲を見渡し、誰も居ないことを確認してから、塔屋の裏側へ。そこには数人が暴れられるくらいのスペースがあり、遠い昔の偉人なのだろうか、立派な石像が立っている。
その横に腰を下ろし一呼吸。
柔らかな風が頬を撫でる。春らしい陽光が辺りを包み、重たい気持ちが少しは軽くなった気がした。
よく晴れた空を見上げ、これからの事に思考を向ける。
最善はやはり、何時も通りの関係に戻ることだ。
始まる予兆を感じ取った段階だが、今朝のちぃの態度。あの数時間にちぃの笑顔を見ていない時点で、もう何かが始まってしまっている気がする。
ただの体調不良だとしても、今日のような事は無かった。私が避けているとしても、教室で笑顔が途絶えたのは初めてではないだろうか。
そしてだいちゃんの事だ。
もし、明日以降も今日の様な気持ちが続くのならば、すこし態度を改めなくてはならないだろうか。
私の気持ちを自制するしかないが、あの光景が取り戻せるのならば頑張れる様な気がする。
果たして出来るだろうか。好きな人が他の人と仲良くしているのを遠巻きに見守ることに、私は耐えられるのだろうか。
現状では自信はあるが、やってみないと分からないというのが本心かもしれない。
それに良く考えれば他人じゃない。親友と好きな人の仲がいいのは、むしろ喜ばし事じゃないか。
そうなのだ、あの二人が楽しそうにしていると私も楽しい。
そう考えると簡単だと思った。私の気持ちを殺すくらい、容易いことだ。
とりあえず、今日だけは全てから逃げなければいけない。今朝の夢も今ではそれほど気にならない。今日を乗り切って、明日から何時もの私たちに戻るのだ。
結論に達すると気が緩んだ所為か、お腹が減ったことに気づく。
手元にお弁当が無いことに愕然とする。何故持ってこなかったのだろう、このままでは午後の授業が辛くなってしまう。かと言ってここから出る勇気もない。どこで鉢合わせるか分からないのだから。
吐息と共に空を見上げた時だ。遠くの物音を鼓膜がキャッチする。
屋上の出入り口付近だろう、扉が勢い良く閉じる音だと気づいたのはすぐだった。
誰かが屋上に上がってきたのだ。見知らぬ生徒が私の様にたそがれに来たのか。はたまたこの春の空気を吸いに来ただけなのかも知れない。
しかしこの時の私には、言い様の無い悪い予感しか存在しなかった。
塔屋の壁に沿いながら側面に移動し、身を隠しながら出入り口付近を覗き見る。
いる。男子生徒だろう。左手に小さな包みを手に、辺りを見渡しながらこちらへと歩み寄ってきている。
その姿が鮮明に映し出す頃、私の瞳はしっかりと確認する。
――だいちゃんだ。
何故? どうして? そんな疑問しか支配しない思考をどうにか振りほどき、この場から逃げることに専念する。
たぶん、だいちゃんもここを知っている。ここに来る可能性も十分ありえる。
見つからずに屋上から出るには、だいちゃんが石像に到着する頃には私が出入り口に居なくてはならない。
距離的に絶望感が漂うがやるしかない。物音厳禁。聴覚集中。慎重且つ大胆に。
耳を澄ませ足音に集中する。まだだ、もう少し……。……もう少し。
こういった状況下での時間と言うのは、なんとももどかしい物だ。他の事に集中している所為か時の流れを忘れてしまう。
そろそろだろうか、私の全感覚ではだいちゃんは今、塔屋の私とは反対側付近に差し掛かっていると告げている。ここいらで行動しないと間に合わないと判断し、塔屋の正面側へと踊り出ようかとした時だ。
「お前、なにやってんの?」
今世紀最大の驚きが私を襲う。全神経が逆立ち、その勢いで腰が抜けそうになる。
それに私自身、出した事の無い悲鳴の所為だろう、振り返るとだいちゃんが呆れた顔をして立っている。
こういう時こそ忍者になりたいと本気で思ってしまう私は、結構浅はかなのかもしれない。
「まぁいいや。ほれ、お前の弁当だろ? 持って来てやったぞ」
見たことの無い笑顔でだいちゃんが包みを差し出す。その笑顔は今までどこに隠していたのだろう。
不覚にもその顔を見つめてしまった所為か、今朝の夢がフィードバックし、途端に顔が熱くなる。
どうしたらいい? 逃げるべきなのは分かっているのだが、身体が微動だにしない。それに目が離せなくなっている。
今まで何一つ気にしなかった笑顔が、今ではとても眩しく輝いて見える。この笑顔を見ていたい。何時までもこの笑顔の傍にいたい。
そんな想いが抑え切れないほどに膨れ上がり、私のあらゆる感情を満たしてゆく。
なかなか受け取らない私を不振に思っての行動か、近づき顔を覗き込んでいる。
ひゃっ。そんな控えめな悲鳴と共に顔を背けるのが精一杯だった。
「どうしたんだ? おかしいぞ、おまえ」
言われなくても自覚している。ここまで動揺し、どうしていいのか判断が出来なくなってしまうなど、誰が予想する。
「とりあえず飯食えよ。落ち着くかも知れんぞ」
そう無理矢理お弁当を押し付けられる。
手に持ったお弁当を見つめ、本気でどうしたら良いのかと考える。
まずは何か言わなければならない、だいちゃんが此処へ来て、今だ悲鳴だけで対応しているというのは恥ずかしすぎる。
お礼。そうだ、お礼を言わなければ。
しかし、それすらも今の私にはとても難しいことの様に思われた。
とてつもなく恥ずかしい。ただのありがとうが、訳もなく違う意味に捉えられるのではという不安が支配する。
この時の私は『ありがとう』と『好きです』が同義語のような錯覚に陥っていのかもしれない。
「あ。あありがとう……」
それでもどうにかして搾り出す。それと同時に相手の反応が無性に気になり、だいちゃんを見遣ってしまう。
苦笑だろうか。しかしその苦笑が暖かく感じ、笑顔の様な気もしないでもない。
なんだか安堵してしまうその表情を見ていると、少しずつ身体が動くようになってきた。
しかし思考の方はまだ混乱している様で、この次は何をしたら良いのか未だに判断が出来ないで居る。
「……? どした?」
その言葉に慌ててしまう私は、何を思ったのか、立ったまま包みを解こうとし、お弁当を落としそうになる。
すかさず手を差し伸べ、支えてくれるだいちゃん。
「あっ、ごめん。はは、何やってんだろ、私」
ほんと、何やってんだろう。
その場に座り込み、包みを解いてゆく最中、ちぃのあの表情が脳裏をかすめる。
こんな状況をちぃに見せる訳には行かない。
今の私たちの関係が拗れてしまうのではないか、そんな嫌な予感がするのを黙って無視するなんて出来ない。
「ありがとう。もういいよ」
笑顔でそう言ってみるが駄目だった。
「え。俺ここに居たら駄目か?」
「駄目じゃないよ!! ……駄目じゃ、ない」
声量の大きさに二人して驚いてしまう。
反射的に嫌われたくないという気持ちが私をそう叫ばせていた。
先ほどの事といい、今の事といい、自身に驚きっぱなしだ。それに一人になろうとしたのに、必死で引き止めてしまっている。
もう何が正解で何が間違えなのか全く分からない。
今の今までどのように接していたのかも思い出せない。
お弁当のおかずを口に放り込むが、何を食べているのかすら分からない。この世界は分からない事だらけで戸惑ってしまう。
しかし、そんな状況でも自覚してしまう気持ちがあった。
もうこの感情からは逃げられないのかもしれない。
だいちゃんが腰を下ろす。
その仕草にすらビクついてしまう。
なんだか全てを放り出して、走り去ってしまいたい気分だ。
お弁当に集中しよう。そう思い箸を動かしてゆく。そしてふと穏やかな空気が流れていることに気が付いた。
だいちゃんの顔を直視できないでいるが、今流れているこの雰囲気はとても落ち着けるものだった。
――いいなぁ、この感じ。ずっとこんな感じで……。
こんな感じでなんだと言うのだろうか。ちぃの居ないこの場の雰囲気が好きだとでも言うのだろうか。
この雰囲気も確かに好きなのだろう。けど、ちぃが居ればもっと良い筈だ。
それにやはり私じゃない。だいちゃんの隣にはちぃが居なくてはならない。それが当然で必然だ。
「あのさ」
居心地の良い沈黙をだいちゃんが小さい声で遮る。
そんな些細な言葉にさえ脅えビクつく私は、一体何に対して恐れを抱いているのだろう。
「……反応、過敏すぎじゃない?」
「そそんなこと無いよ? うん。で、なに?」
何度も首を横に振る私を尻目に、だいちゃんは吐息を一つ。
「んー。何て言っていいかな。俺も少し迷ってるんだけどな」
「……?」
「変なこと聞くけど、いい?」
「その質問によるかな」
「うん。じゃあさ。お前……。……好きな人居る?」
あぁ、なんだろう。どう答えたらいいかな。
とりあえず、頭が真っ白になりつつあるのをどうにかしなければならないのだけど、如何せん、今の私にはその単語は結構タブーな訳で、これ以上意識したら手に負えなくなってしまう。しかもそれをだいちゃんの口から聞かされるともうどうしていいのかさっぱりな訳でして、これはあれかな? 何かの罰なのでしょうかね。
横恋慕をしよう等とは一切思ってないのですが、結果的にそうなってしまっているのでしょうか? いやいや、結果的にとはいえこの仕打ちは酷過ぎやしませんか?
そのような事に時間をたっぷり使った私の回答はこうだ。
「……うん。いるよ?」
アホカ! 素直すぎにも程があるわ!
しかし、現状の思考能力では嘘をつくことが出来ないくらいに低下している。
こういう時こそ八方美人と本気で罵られたい私は、もう駄目なのかもしれない。
「そうか。お前も恋してるのか」
「そう……なるのかな」
「楽しいか?」
「恋がって事? そうだね。あぁでも辛い事の方が多いかもね」
そんなささやか会話が、今は一番楽しかった。
際どい会話だけれど、これがもし私の好きな人がだいちゃんでは無く、なんの気兼ねなく話すことが出来たのならと考えてしまう。
「その恋。叶うといいな」
そう言ってくれるのはありがたい。けど……。
「私のは叶わないよ。と言うかね、叶って欲しくないんだ」
「どう言う事?」
「それは言えない。いくらちぃの幼馴染のだいちゃんでも、これだけは聞いて欲しくないかな」
そう。私が欲しているのは今のこの状況じゃない。
足りないのだ。この場にあと二人必要なのだ。
自然に顔を上げることが出来、だいちゃんを見ることが出来た。
しかし、見なければ良かったと後悔が押し寄せる。
だいちゃんの表情はとても険しく、なんだか少し苦しそうだった。
その表情を見た瞬間、辺りに渦巻く得体のしれない物が取り付いてゆく。
「なに? どうしたの……」
嫌な予感が私を支配し、そんな台詞を口にしていた。いや、聞かなければ良かった。
一変したこの空気を感じ取りながらも、問いかけてしまった事に後悔する。
こんなにも雲行きが怪しいのに、そこに足を突っ込んでしまうのは自殺行為に等しい。
どれだけ祈ったのだろう、私の勘違いで終わって欲しいと。どれだけ願ったのだろう、私の思い過ごしであって欲しいと。
しかし、その願いが届くことは無かった。
だいちゃんは深い溜息と共に空を仰ぎ見る。
「やっぱり、ちぃか……」
その台詞に、私が持っていただろう何かが崩れ去る。
それと同時に加速してゆく感情。
「……やっぱりって、どういう意味」
感情が切れてゆく。そして新たな感情が結び合わさり、感じたことの無いモノに形成される。
「ん。いや、なんでもない」
「なんでもなくないでしょ。なんでもなくないよ? なんでもなくないよね」
無意識。いや、意識はしているのだが抑えきれない。
一度変わってしまったこの空気を元に戻すなんて、今の私には無理だった。
「だいちゃんは今ちぃの事を思って、そんな表情な訳だよね。どうしてそんな落胆してるの? まるで邪魔者だと言わんばかりに」
「どうし……」
「どうしたの?! それはこっちの台詞よ! どうしてそんな態度になるんだよ! どうしてちぃの事を考えてそんな表情が出来るんだよ! 分かってんでしょ? ちぃはだいちゃんの事が好きなんだよ?! あの態度を見て気づかなかったなんて言わないよね? なんで答えてあげないの? どうして傍に居てあげないのよ?! どうして此処にいるんだよ!!」
息を切らしまくし立てる。いつの間にかその場に立っていたらしい、そのままだいちゃんを見下ろす。
違うと否定して欲しい、私の勘違いだと訂正して欲しい。
音も無く立ち上がるだいちゃんは私を真剣に見つめる。
「俺が此処にいる理由を知りたいか?」
嫌だ。
「弁当を持って行ってくれと、ゆーこに頼まれたんだ。でもそれだけじゃない」
いやだ。
「俺は此処に居たいから居るんだ。だから俺はお前が……」
「いや!!」
こんなのまちがってる。
「それ以上聞きたくない……」
「おれは!」
「聞きたくないって言ってるでしょう!?」
睨み付ける。こんな表情で人と相対したのは初めてのことだった。
決してだいちゃんが悪い訳じゃない。そんなこと分かりきっている。全て私の身勝手なのだ。
「もう、用事は済んだよね? 出てって」
何時までもあの愛おしい時間が続くなんて不可能だと理解していた。
「今すぐ此処から出てってよ!!」
それでも私の行動で、それが可能である事も知っていた。
ちぃが居て、ゆーこが居て、だいちゃんが居る。みんなと同じ時間を、同じ気持ちを共有し笑って過ごす。そんな時間を私は欲した。
そう祈るだけだった。
自身の気持ちを無視し続け。相手の気持ちを無視し続けた。
私が少しでも早くだいちゃんへの気持ちに気づき、距離を置くことも不可能ではない。
私が滑稽なのは自身の気持ちにさえ、耳を傾けなかった事だ。
何時からだろう。だいちゃんが気になりだしたのは。
何時からだろう。だいちゃんを好きになり始めたのは。
何時からだろう。だいちゃんを好きになってしまったのは。
そんなことも分からない。
自身で作り上げようとせず、もう少し、もう少しだけと言いながら、最後は神頼み。
滑稽すぎる。そして愚かすぎた。
少しの辛抱を後回しにし、結局壊れてしまった。
私自身の手で、捨てたと言っても差し支えない。
私が望む世界を私自身の手で壊したんだ。
空を仰ぎ見る。
誰も居ない屋上が春の陽気で包みこまれ、緩やかな風が頬を伝う熱いものを冷ましてゆく。
これからの事なんてどうでもいい。
全てを投げ出し、独り声を殺して泣き続けた。